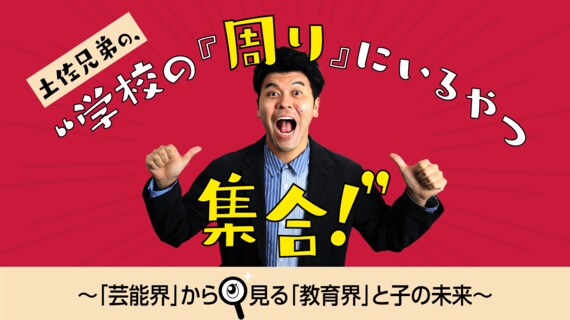B先生:親は人生経験を積んでいるので、夢を叶えられた人もいれば、叶えられなかった人もいることをよく知っているわけです。子どもがハイリスクな道を歩もうとしていたら、口を出したくなる気持ちもわかります。
A先生:最近は、保護者が「キャリア部」なるチームを作って、生徒向けに座談会形式の研修を企画する学校もあるようです。今の親は、ビジネスパーソンは世の中が激しく変化していることを知っているので、子どもたちには自分でキャリアを切りひらく力を養ってもらいたいと思い始めているのでしょうね。
卓也:保護者のキャリア部、すごいですね! 教員の負担も減るし、いいアイデアかもしれません。今はネットの時代ですし、「何者」かになるきっかけも増えています。学校がキャリア教育に注力する以前に、子どもも内心では「これをしてみたい」と考えているかも。そうした話を聞いてくれる大人も必要ですね。
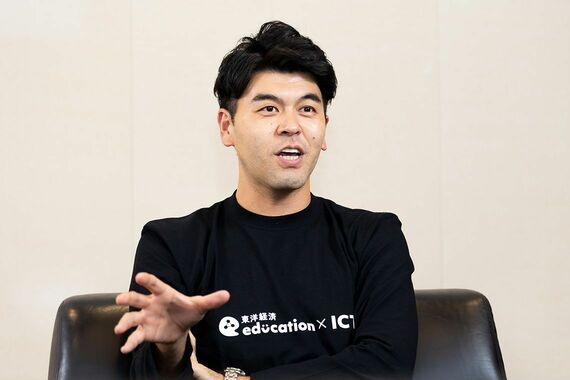
B先生:細かい年号とか、ヨーロッパの学生でも知らないようなローマ皇帝とか、そんなことを教えるよりは、キャリアカウンセラーに相談する時間のほうが、よほどためになるでしょうね。せっかく秀でたものがある子が受験戦争で疲弊して消費されてしまうのはもったいない。
A先生:暗記したローマ皇帝の人数でしか生徒を差別化できない日本の評価体制も疑問ですよね。実は、キャリアカウンセラーもちょっとずつ増えていて、公立中学校への配置を推進すると明言した自治体もあります。とはいえ、ノルウェーやアメリカなどの諸外国と比べるとまだまだ少ない。理由は、日本の教育では教えることが多すぎるからです。文科省がキャリア教育を推進するのはいいですが、ほかの業務も残したままやろうとするから進まない。学校側もキャリア教育を教員だけでやろうとするのではなく、保護者や企業、NPOなどうまく協力先を探すのがよいと思います。
C先生:キャリア教育が浸透すると、学歴に依存せず、「自分がこれをしたいからこの大学に行く」と進路を選べる子が増えるでしょう。勉強もプライベートも、すべての経験が自分のアイデンティティであり、ひいてはそれがキャリアになります。変化の激しい時代だからこそ、誰かが決めたレールを歩くのではなく、自分らしいキャリアを考えてほしいですね。
卓也:僕は、会社員からお笑い芸人に転向した瞬間に、思いっきりレールから外れたキャリアを歩んでいます。これまで、売れた芸人、売れずに辞めた芸人、違う道に進んで成功した芸人もたくさん見てきました。でも、いつだって自分が本気なのであれば失敗してもいいと思うんです。突き詰めれば楽しく生きることが重要ですから、まずは大人自身が楽しく働く姿を子どもに見せてあげることかな。今は、メディアやYouTubeを通していろいろな経歴の人を見つけやすい時代なので、子どもたちには楽しそうな大人をたくさん見てもらう。そしてキャリア教育も、時代に合わせてアップデートされていってほしいですね。
(文:末吉陽子、撮影:今井康一)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら