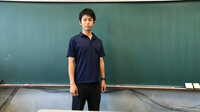定時退勤のカギは「教師の力量」向上に尽きる訳、働き方改革での管理職の役割 学校教育本来の役割、教師の仕事の本質とは?
働き方改革における管理職の役割とは、職員が充実感とやりがいを持って仕事に取り組む環境をいかに実現するかだ。時間外勤務短縮のために管理を強化したり効率重視の働き方を徹底したりすることではない。慣例的に行われているさまざまな働き方を精査して、改めるべきは改めてすべての職員が負担なく働くことができる体制を作ることも、その1つだ。
例えば、職員が互いの立場を理解し合い、それぞれのペースで仕事に取り組み、自己都合と自由意志で退勤時間を選択することができる職場にすることである。
教師一人ひとりが、未来を担う子どもたちを育て導くという教職に誇りを持って働くように導くことである。協同的な教職員組織や力量を高め合うことのできる関係を築くことが、働き方改革を実のあるものに導く管理職の務めである。
「真」の働き方改革のために
子どもの成長と笑顔に、喜びと生き甲斐を感じるのが教師だ。「子どものためであれば」と、誰に命じられることなく進んで時間と労力を費やすのが教師の「性」である。
だから、時間外勤務を短縮するだけが働き方改革ではないと私は考えている。喜びと生きがいを感じられるのであれば、時間外勤務が少々多くなったとしても、心身の負担を感じることは少ないだろう。もちろん、自分や家族の時間を確保するために、より効率的な働き方を工夫しなければならないという前提でのことである。
問題なのは、保護者や管理職、同僚など周囲の評価を気にして行う仕事のやり方や、教師として意味を感じられない仕事ではないだろうか。そして、「教職はブラック」と言わしめる最大の原因にもなっているトラブル対応や保護者対応である。
児童生徒の学校生活で生じる人間関係のトラブルやケガなどに対しては、昔では考えられないほど丁寧な対応が求められるようになった。少しでも対応を間違えると、保護者から想像以上に激しい苦情が出る危険性がある。
そのため多くの教師は、神経をすり減らしながら細心の注意を払って仕事をしているのが現状である。現在、学校現場は、過度とも思われる期待と責任に必死で応えようともがいている。
このような、保護者を過剰に意識した「懇切丁寧」な児童生徒への対応は、本来、成長のために必要な人間関係や危機回避を学ぶ大切な機会を、子どもから奪ってしまっているようにも思われる。
私たち教師を含め、子どもと関わるすべての人が、学校教育本来の役割とは何か、教師の仕事の本質とは何かを真剣に考える時期が来ているのではないだろうか。それこそが、「真」の働き方改革を実現する重要なファクターとなるはずである。
(注記のない写真:Graphs / PIXTA)
執筆:奈良県公立小学校 校長 中嶋郁雄
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら