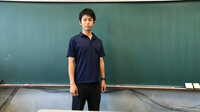定時退勤のカギは「教師の力量」向上に尽きる訳、働き方改革での管理職の役割 学校教育本来の役割、教師の仕事の本質とは?

「働き方改革」が好意的に受け入れられていない?!
学校現場の過酷な実態が明らかになって以降、「働き方改革」が文部科学省から教育委員会を通じて急速に推進されている。
しかし、学校現場に身を置いている者としては、「働き方改革」が多くの教師に好意的に受け入れられているとは言い難い。管理職による強制的なノー残業デーの設定や定時退勤の勧奨は、教職員の反感を買う危険性さえはらんでいるというのが、多くの小中学校の実態ではないか。
「山のようにある仕事を放り出して退勤などできない」「課題を抱える児童生徒や家庭が多いため、早く退勤するなんて不可能」と、はなから定時退勤に否定的になっている教師は少なくない。
今、社会の変化に伴って、教育現場にも急速な変化の波が押し寄せており、教師の多忙を招く一因になっている。また、保護者や地域住民からの要望にも応えなければならないという「空気」が、教師の時間を奪う原因にもなっている。
確かに、教師の仕事には際限がなくなってきているものの、時間も無限にあるわけではない。本来、最も時間を割かなくてはならない授業研究や子どもと触れ合う時間を確保するためにも、時間の効率的な使い方が重要になる。
マインドセットの見直しを、まずは心がけから
例えば、宿題チェックやテスト採点などは、授業の合間にできるわずかな時間を使って少しずつ進めるよう心がける。校務分掌の仕事も、職員室に戻ってくるわずかな時間に、できるものから少しずつ片付けていけば負担なくやり終えることができる。

奈良県公立小学校 校長
1989年奈良教育大学卒業後、奈良県内の小学校に勤務。「子どもが安心して活動することのできる学級づくり」を目指し、教科指導や学級経営、生活指導の研究に取り組む。子どもを伸ばすために「叱る・ほめる」などの関わり方を重視することが必要との主張をもとに、「中嶋郁雄の『叱り方』&『学校法律』研究会」を立ち上げて活動。著書に『校長1年目に知っておきたい できる校長が定めている60のルール』『仕事に忙殺されないために超一流の管理職が捨てている60のこと』(ともに明治図書出版)『残業しない教師の時短術 フツウの教師・デキる教師・凄ワザな教師 』『信頼される教師の叱り方 フツウの教師・デキる教師・凄ワザな教師』(ともに学陽書房)などがある
(写真:中嶋氏提供)
「時間がないから……」と、ほんのわずかな時間を無駄に過ごすと、結局10分間も20分間も何もできずに、無駄にしてしまうことになりかねない。「すき間時間に、少しでも何かをやろう」と意識して行動することで、たとえわずかな時間であっても、ある程度の仕事を進めることが可能になる。