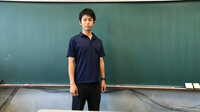定時退勤のカギは「教師の力量」向上に尽きる訳、働き方改革での管理職の役割 学校教育本来の役割、教師の仕事の本質とは?
できる仕事にはすぐに手を付けることも重要だ。後回しにすることで、日が経つにつれてほかの仕事と重なり、時間の余裕も気持ちの余裕も奪われることになる。また、「書類を10分間で終わらせる」「この時間にできるところまでやる」など、時間を意識することが仕事の効率化を促し働き方を変えることにつながる。
こうした学級事務や校務分掌の仕事は、効率化と時間の捻出方法を工夫することでクリアできるはずだし、できるよう努力しなければならない。
問題になるのが、喧嘩やケガなど学校で生じたトラブル対応のために、勤務時間外に保護者と連絡を取らなくてはならないような場合である。学校外での児童生徒の問題行動で、夜遅くまで地域や警察などの関係機関への対応が必要になる場合もあるだろう。突然生じたトラブルで、勤務時間内に仕事を終えることが難しい場合は起こりうる。
しかし、たとえ児童生徒のトラブルや保護者・地域対応が多い学校であっても、定刻を大幅に超えて勤務しなくてはならない状況が、毎日続くわけではないはずだ。トラブルの多い学校に勤務していても、働き方を変える努力から逃れてはならない。何のトラブルもない時に、教師それぞれが定時退勤を心がけることが大切である。
定時退勤を実現させるための重要なポイント
昔から教育現場には、子どものために労力を費やすのが当たり前という暗黙のルールが存在する。現在も「子どものため」だからと時間を費やしている教師は少なくない。
もちろん、子どものために時間を費やすことで、やりがいと充実感を得るのはすばらしいことである。しかし、とくに若い時分は、限界に気づかず時間を費やしてしまう危険がある。限界を超えてまでする仕事は、単なる自己満足に過ぎない。体力と気力を蓄えて、元気に子どもに臨むことが真に「子どものため」であろう。
そのためにも、自分の能力や生活リズムを把握したうえで、仕事に費やす時間を考える必要がある。そうすることにより、限られた時間でいかに効率的に仕事をするか、真剣に考えるようになるはずである。
こう考えると、定時退勤を実現させるための重要なポイントが見えてくる。
トラブル対応に割く時間と労力を削減して、教材研究や事務処理など自分のペースで進めることができる仕事に時間を充てられる状態を作り出すことが、定時退勤を実現させる条件である。では、このような状態を作るためにはどうすればよいか。
それは、児童生徒の学校生活を安定させることに尽きる。
児童生徒の学校生活の安定を保証するためには、教師の学級経営力量や授業力量、そして生徒指導力量を高めることが必要である。登校しても授業がつまらない、クラスに居ても居場所がない、相談したくても教師が頼りない……。そのような状態の学校で、児童生徒のトラブルが起きないはずがないのである。
授業力量や学級経営力量といった教師に必要な力量を高めることによって、児童生徒は安定した学校生活を送るようになり保護者からの信頼も得られる。結果、トラブル対応にかける労力は不要になる。
児童生徒や保護者と良好な関係が構築され、トラブルが少なくなることで、定時退勤可能な状態が日常になっていく。定時退勤を実現する重要なポイントは、教師力量向上へのたゆみない努力である。
働き方改革を実のあるものに導くのは管理職
長時間勤務になってしまう原因の一つに、児童生徒が下校した後に行われる学年部会や専門部会などの会議(話し合い)がある。
それらの会議が、退勤時刻を過ぎても当たり前のように行われる学校があると聞く。ひどい場合は、退勤時刻を過ぎてから会議がスタートすることもあるようだ。職員の中には、子育てや親の介護などさまざまな家庭事情を抱えている者も多いはずである。