貿易摩擦下の日米が激しくやり合った30年前の通商交渉。その教訓を双方の当事者たちが振り返る。

雪が降っていた。しんしんと降っていた。
1994年2月11日午前4時すぎ。米ワシントンの通商代表部(USTR)。2階の「203号会議室」から羽田孜副総理兼外相らの一行が足早に降りてきた。
ミッキー・カンターUSTR代表との話し合いがまとまらなかったのだ。その瞬間、数時間後に開かれる日米首脳会談の決裂が確定した。戦後初めてのことだった。
「日米合意せず」もありうると考えていたのは、通商産業省(現経済産業省)の米州課長だった豊田正和氏。担当者として、このときはワシントンに滞在していた。
「それまでの交渉で両国の立場には違いが大きいこともわかっていた。米国との場合、いつもは日本側が譲歩して交渉をまとめようとするが、このときは違った。主戦論も強かった。細川首相も筋を通す人だと知っていたので、交渉妥結は難しいだろうと思っていた」


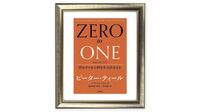





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら