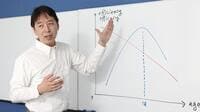「英単語帳使わない塾」、大学受験グノーブルが問う塾業界と英語教育の違和感 生徒を「合格実績稼ぐ道具」にするのはおかしい
さらに、オリジナルの英語音声教材「GSL(Gnoble Sound Laboratory)」では、ウェブサイトやYouTubeにて教材をネイティブのナレーションで配信。高3のカリキュラムでは、1分あたり180語というCNNのニュースと同等の速度の音声教材を毎週(1年間で55本)提供している。
「音声学習は、『聴き込み(文章を見ながら音声を聴く)』『口まね(文章を見て音声を聴きながら口に出す)』『音読(文章を誰かに伝えるつもりで読む)』というステップで進めます。慣れると、英語の語順のまま左から右へ、返り読みせず理解できるようになります。音読した英文は頭の中にも残りますから、それを真似れば自然な英文も書けるわけです」
英語教育は「中身ない会話をペラペラ話すこと」が目的でない
近年の大学入試は、「英語は文章量が大幅に増加し、難度も高くなった」と中山氏。しかし、必ずしも受験生の学力レベルの向上までを意味するわけではないという。
「大学の中で、数年前なら不合格だった学力層の生徒が合格できている例もありますが、入試問題は難しくなっていて受験生のレベルが追いついていないように感じます。一方で、東大・京大・一橋大などでは感動させられる良問も多く、『こんな学生に来てほしい』というメッセージを込めた出題をする大学がほかにも増えることを期待しています」
入試の難度が上がっていることを踏まえて、学校教育はどう変わる必要があるか。日本の学校における英語教育について、中山氏は「表面的な流暢さを一義的にすべきではない」と見解を示す。
「大事なのは、中身のない会話をペラペラ話せることではなく、やはり知的レベルの高い考えや意見を受信・発信できることだと思います。日常会話であれば誰でもできるようになりますが、例えば『本を読む』にはある程度の言語能力が必要でしょう。
オールイングリッシュの授業をする学校もありますが、拙い英語で表面的なやり取りで終始することになり、論理力の向上にまで至っていないケースも見受けられます。複雑なことを考えるには、補助的に日本語を活用して理解することも大切。英語は慣れるだけでは不十分なのです。これは学校教育にも、私たち塾業界にも求められていることだと思います」
(文:安永美穂 編集部 田堂友香子、注記のない写真:東洋経済撮影)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら