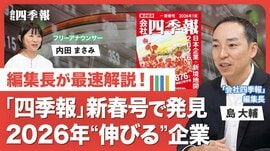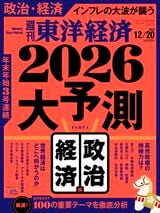子ども追い込む「エデュケーショナル・マルトリートメント」が日本で起きる訳 「勉強していい学校に行っておかないと」の影響
こうしたマルトリートメントは、とくに儒教の影響が強い国やカースト制度が残る国など上下関係を重んじる社会で起こりやすいという。そう考えると今の日本では、家庭で父親が絶対的な力を持つ家父長制の影響が弱まっており、エデュケーショナル・マルトリートメントが抑止されてもよさそうだが、それは逆だと武田氏は話す。
「昔は祖父母や親戚のおじさん、近所の人など、いろいろな大人と接する機会があり、生き方のモデルが身近にありました。また、親に叱られても祖父母の元に逃げ込んだり、親子げんかを近所の人に仲裁してもらったりということができました。しかし、今は核家族が増え、子どもは学校や塾、学童と家の間を往復する毎日で、地域に暮らすいろいろな大人と接する機会がありません。密室の中で大人の言うことは絶対という中、強い力でコントロールしようとすると、子どもにもろに影響が出てしまいます。家父長制が強かった時代にも、子どもを殴る頑固おやじはいましたが、家族や社会は閉じていませんでした。家族や社会が閉じている今、大人も子どもも逃げ道がなくなっているのです」
「こうあらねば」に追い詰められる大人
こうしたマルトリートメントな社会を象徴する出来事として、武田氏は1つの例を挙げる。
「ある女優さんが、成人を過ぎた子どもが犯した罪で責められたことがありました。あの時、日本中の母親の多くが『子どもが罪を犯せば母親や家族が責められるのだ』というメッセージを受け取ったのではないでしょうか。だからこそ『ちゃんと育てなければ』『いい教育を与えなければ』とプレッシャーを感じ、子どもにきつく当たってしまう。しかし、家族も社会も閉じているので、逃げ道を失ってしまうのです」
そもそもマルトリートメントな社会の被害者は、子どもだけではない。親や教員などの大人も「こうあらねば」という圧力を受けて育った可能性が高く、自分がマルトリートメントを受けて育ってきたという認識がないことも珍しくない。そこでまずは、自分がマルトリートメントを受けてきたならば、そのことを自覚することも大切だという。
では、大人がマルトリートメントを予防するためにできることはあるのか。いい人生を歩んでほしいと願うのが親心であり、何でも子どもがやりたいように自由にさせるというのはなかなか難しそうだ。
「子どもの立場に立って、ハードルを上げすぎず、目標設定が適切か、どういう関わり方が適切かを考えなければなりません。子どもが大人の顔色をうかがったり、大人に何も言わなくなったら、不適切な関わりがあるということだといえます。今は、いい学校、いい教育を目指してしまう社会環境にありますが、学ぶことが嫌ではない大人に育つことを目指すので十分ではないでしょうか」
変化の激しい社会では、求められる知識や技能が時代によって変わる。生きていくうえで必要に応じて主体的に学ぶ力が求められており、学ぶことが好きになる、学び方を学ぶ場としての学校現場の役割も大きい。
また、国連の「児童の権利に関する条約」や、日本で施行された「こども基本法」を読んでみるのもお勧めだという。
「子どもの権利というものは、大人が上から目線で『大変な状況の子を守ってあげる』ようなものではありません。日本語の『権利』は堅苦しいイメージですが、英語のライツ(rights)には『自然で当たり前のこと』という意味があります。つまり、権利は人として当たり前に持っているものなのです。例えば、まだ話せない新生児の『あー』とか『うー』という訴えに対し、ケアする余裕のある大人が『どうしたの?』とやり取りして、相手の立場で要望を聴き取る。そうされて初めて小さな存在でも社会に認められる。そういうことなのです。