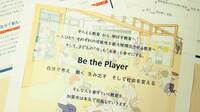「最大3600万円の給付型奨学金」足立区長・近藤弥生が教育に力を入れ続ける訳 「教育は経済的な格差を埋める最強の武器」
2023年度から奨学金の給付がスタートしたが、よりよい支援となるようすでに調整を考えているという。
「医学・歯学系は学費がかなり高いため、医学・歯学系に関する所得制限については、今後の応募状況を見ながら改めて検討していきたいと考えています。また、きょうだいが多ければ子ども1人にかけられる学費も限られます。より立体的に条件を検討し、支援の内容を進化させたいと考えています」
足立区は、20年から「足立区奨学金返済支援助成」も行っている。これは対象の奨学金の貸し付けを受けている、または受ける予定の高校生・大学生に対し、借入総額の半額(上限100万円)を助成するというものだ。「今後は、今返済されている方々の負担軽減策についても検討していきます」と近藤氏は言う。
「出産した人への支援も大事ですが、若い世代が『結婚したい』『子どもが欲しい』という気持ちになるには、経済的な自立が必要です。もちろん結婚や子どもを持つことを望まない人もいるので、そう考える人を無理に変えるつもりはありません。ただ、若い世代が家庭を持つことを望んだときに、一歩踏み出せるような支援をしたいと考えています」
足立区が抱える「4つのボトルネック的課題」
足立区ではこれまでも、教育資金の支援だけでなく、基礎学力の定着を図るための個に応じたきめ細かな指導や、学習意欲が高い中学生向けの学習塾「足立はばたき塾」(関連記事:「学力トップ層向け『はばたき塾』が話題の足立区、ほかの教育施策もすごかった」)など、さまざまな学習支援策も展開してきた。
手厚い教育施策を進める背景には、「①治安、②子どもの学力、③健康寿命の短さ、④貧困の連鎖という4つのボトルネック的課題(※)がある」と近藤氏は指摘する。
※克服しない限り区内外から正当な評価が得られない根本的課題
「経済的に厳しいと健康が二の次になり、健康に問題があれば働けなくなって貧困になります。また、働かなければいけない状況では学歴は二の次に。4つのボトルネック的課題はすべてが影響し合っており、貧困の連鎖を断つためにはやはり子ども支援が必要なのです」
「足立ミライゼミ」も、そうした思いから今年度スタートした支援策だ。これは区内在住の高校1年生を対象に、塾などでの学習機会が少ない成績上位者の難関大学合格をサポートするもの。足立はばたき塾の高校生版だ。
「義務教育は中学校までなので、その先の支援までは行ってこなかったのですが、区立中学や高校の校長先生、東京都、NPOなどが参加する若年者支援協議会を通じて、頑張って高校に進学しても家庭の経済力は変わらないため苦労は続くという課題が見えてきたのです。例えば、足立ミライゼミで大学に合格したら、今度は区の奨学金で大学に通うといったことができるように、高校進学後も切れ目のない支援が必要だと考えました」

このように、支援策は現場の声から実現するものも多い。
「今年から部活動費や課外活動費、資格取得などの費用として年額5万円支給する『高校生応援支援金』を始めましたが、これも校長先生から『道具を買う費用や遠征費が出せず、クラブ活動が“贅沢”になっている子がいる』と聞いたことがきっかけです。家庭で朝食が提供されず、授業に集中できないお子さんに対して学校が補助食を提供できる費用の補助も、現場の先生方の声を基に始めました」
足立区では、子どもたちの将来を見据えてICTの活用も推進している。2022年度からは小中学校でAIドリルを全校に導入し、個に応じた学習に役立てている。