かまいたち山内健司が明かす「教員の道を選ばなかった本当の理由」 「働きたい企業は1つもなく」独自のキャリア論

頑張る先生がもっと報われる「内申点システム」が必要
一方で、2児の父親でもある山内さん。今年で5歳と1歳になる子どもの教育では、自身の効率重視の考えを子どもに勧めるつもりはないそうだ。
「いろいろな知り合いから、『この学校に入れたほうがいい』とか『ここに入れれば将来有利だ』とアドバイスをいただくんですが、ピンとこなくて。いくら親がお膳立てしても、本人に火がついていなかったら意味がないのだろうなと思っています。
無駄なことをしてからじゃないと、どれが効率のよい方法かはわからないと思うんです。大人から見たら無駄に感じることでも、まずは何でもやってほしい。そして自分の力で、効率のよい人間になってほしい」

そんな山内さんに未来の学校教育への期待を聞くと、「もっと先生が評価される仕組みがあってもよい」という答えが返ってきた。
「警察官なんかもそうですが、先生は“縛り”が多い職業です。問題を起こしたら一発でアウト。でも親は『先生はみんなちゃんとした人』と信じているからこそ、大切な子どもを預けられます。だから正直、一度学校に入ってしまえばずっと教員をしていられる状況は望ましいと思えません。熱意がなくなったのなら先生を辞めてよいと思う。
もちろんその分、先生の給料は保証すべきだし、先生には給料に反映される内申点のようなシステムがあってもよいのではないでしょうか」
そう考えるのは、山内さん自身が教育実習で無力感を味わったことと、中学生時代にユニークな評価システムを導入する教員に出会ったことが影響していそうだ。
「理科の先生で、挙手したら1点、的を射た質問をしたら3点、挙手ができなくてもノートを提出すれば得点、など、テスト以外でも積極的に授業に参加することを評価してくれた先生がいました。生徒たちにも好評で、みんな面白がっていました」
こうした一つひとつの努力が給与に反映されれば、教員は努力が報われるし、モチベーションを維持できる。
「先生が足りなくて社会人からの採用や臨時採用も増えていると聞きますが、ほかの仕事をしたけどやっぱり先生を目指すという人には、熱意があると思うんです。そういう人たちをもっと受け入れて、先生たちの頑張りが実を結ぶようになってほしいです」
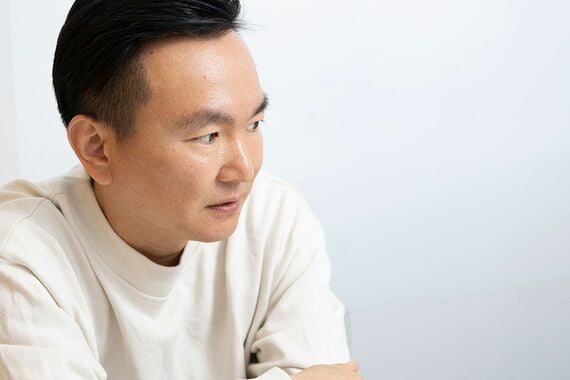
山内さんの理想のように「無駄を省いて効率よく、楽に稼ぐ」には、そもそも職場にこうした働き方を可能にする環境があることが必要だろう。「楽」とは仕事を怠っている状態ではなく、頑張った分だけ手に入れたものを、存分に生かせる状態のことだ。学校現場はいつ、教員が「怠惰を求めて勤勉に行き着」ける職場になるのだろうか。
(文:高橋秀和、編集部 田堂友香子、写真:今井康一撮影)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























