Wi-Fiが飛ぶ森で授業、長野県の小さな公立小に「教育移住者」が増える理由 小規模特認校・伊那西小、学校林をフル活用

森を走りマイツリーを観察、目の前に「学校林」がある日常
西に中央アルプス、東に南アルプスが連なる長野県伊那市。中央アルプスのふもとにある伊那西小に通う児童たちの朝は、読書またはマラソンから始まる。
マラソンの日、児童たちが走るのは校舎の目の前に広がる森の中のコースだ。アカマツやサワラ、コナラなどさまざまな木が立ち並ぶ森の中の土はふかふかで、校庭とはまた違う感触がある。その中を、時には草や木の根などを上手によけながら走っていく。

「子どもたちはこの森のことを『林間』と呼んでいます。1キロメートルあるマラソンコースも、地域の専門家の指導を受けながら、子どもたちが整備しているんですよ」
そう話してくれたのは、伊那西小校長の有賀大氏だ。この森は、伊那西小が保有する学校林である。
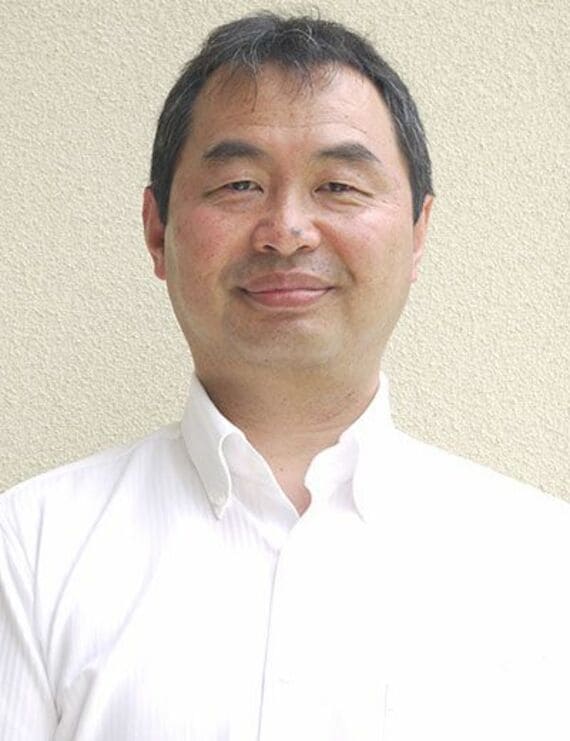
学校林とは学校が保有する森林のことで、教育と学校財産の造成に有効だとして明治時代に児童生徒が植林を行う形で全国に広がっていった。木材需要が高まった戦後の復興期には、当時の文部省と農林省が学校植林を促進。その後も学校林の設置や利用が推進され、学校林保有校(小学校、中学校、高等学校)は、現在も47都道府県すべてに存在する。
しかし、国土緑化推進機構の「学校林現況調査報告書(令和3年調査)」によると、管理の難しさや契約などの問題もあり、1974年に5276校あった全国の学校林保有校は、2233校にまで減っている。こうした中、全国で2番目に学校林が残っているのが長野県だ。小中高合わせて163校(1026ヘクタール)、小学校だけでも95校(474ヘクタール)の学校林がある。
そのうちの1つである伊那西小の特徴は、児童が日常的に学校林の中で過ごし、さまざまな学びに生かしていることだ。
「1年生から3年生の児童は、1人1本『マイツリー』を決めて、その木の定点観測をしています。5年生は野イチゴなどの木の実を収穫し、ジャムを80個作りました。そのジャムを駅前のマルシェに出したところ、1時間で完売。また、春にはタケノコ掘りもします。タケノコは1日であっという間に伸びるので、ちょうどいいタイミングで収穫できるのも、目の前にある林間ならではですね」

「森はぼくらの教室だ」!Wi-Fiも飛ぶ森での授業とは?
四季折々の自然の姿を子どもたちに見せてくれる約1.3ヘクタールの広大な森は、全校行事でも活用されている。

しかし、伊那西小では森を単なる「自然体験の場」で終わらせるのではなく、「森はぼくらの教室だ」というスローガンの下、さまざまな教科学習に生かしている。































