なぜなら、この映画を見た当時、僕は正教員として約10年目にして仕事で大失敗した時期だったから。正直このまま小学校教師として働き続けられるか毎日不安で「何のために教師になったのか」と悩む日々でした。そんな中、この映画に出合って「いま一度、僕も立ち上がろう」「教師としての『何のため』をもう一度追い求めよう」という気持ちになれた。というわけで、いろいろうまくいかないことがある先生にもお薦めかもしれません。
「特別支援教育の視点」は全教員に求められている
2つ目のお薦め作品は、今年4月に公開されたドキュメンタリー映画『僕が跳びはねる理由』です。教育上価値が高いとされる「文部科学省特別選定」にも選ばれているので、ご存じの方もいるかもしれません。
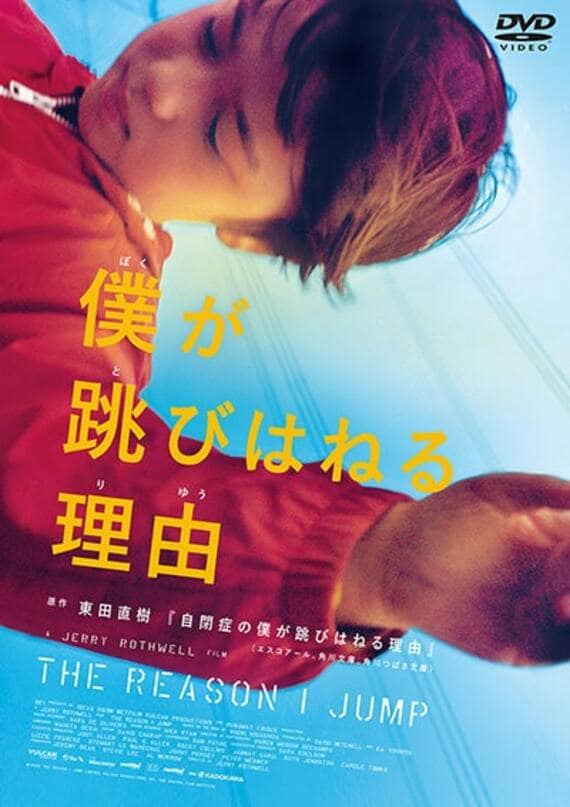
DVD:4180円(税込み)
発売元・販売元:KADOKAWA
この映画の原作は、東田直樹さんが13歳の時に自身の経験を書いたエッセー『自閉症の僕が跳びはねる理由』(エスコアール、角川文庫、角川つばさ文庫)です。
今までは重度の自閉症者には知的障害や認知障害があるとされていたため、自閉症の立場から見た世界が言語化されたことは、日本中に衝撃をもたらしました。さらに、自閉症の子どもを持つ英国の著名作家、デイヴィッド・ミッチェルさんが本書を英訳して話題となり、現在では30カ国以上で出版されているそうです。
そんなベストセラー作家の東田さんを知ったきっかけは、2016年に東田さんを特集した「NHKスペシャル」。重度の自閉症である東田さんは、周りの人と音声でのコミュニケーションを取ることがまったくできない様子でした。しかし、文字盤を使ってタイピングの動作をすると、インタビュアーと会話することができるのです。
その様子に衝撃を受けた記憶が鮮明だったこともあり、英国で映画『僕が跳びはねる理由』が製作されたと知って早速視聴しました。
今、教育現場ではインクルーシブの考え方が広まっていますが、特別な支援の必要な子と共に学ぶ学校・教室をつくっていくうえで、まず教師自身が「知ること」から始めなくてはと考えています。世界各地の5人の自閉症の子どもたちの姿や家族たちの証言を追ったこのドキュメンタリー映画には、そのヒントがたくさん詰まっています。
僕たち大人も含め、誰にでも凹凸があります。それを互いに認め合おう、手を携えて補完し合おうという多様性社会、共生社会の実現に向け、社会は動き出しています。そんな社会で生きていく子どもたちと日々関わる僕たち教員こそ、障害や互いの特性について「知ろう」「理解しよう」と努力を重ねていくべきではないでしょうか。
特別支援教育の視点は全教員に求められていますので、この映画はぜひ教育に携わるすべての人々に見ていただきたいですね。
「読書教育」のヒントが満載、教員にも子どもにもお薦め!
最後にご紹介したいのは、漫画『図書館の大魔術師』です。たまたまTwitterで知り合いがこの漫画を激推ししていたので、「まぁ、読んでみるか」と気軽に読み始めたのですが、「こ、こんな漫画があったのか!」と一気に引き込まれました。読み進めるとタイトルどおり「図書館にまつわる話」が目白押しで、その日のうちに最新刊の5巻まで読んでしまいました。
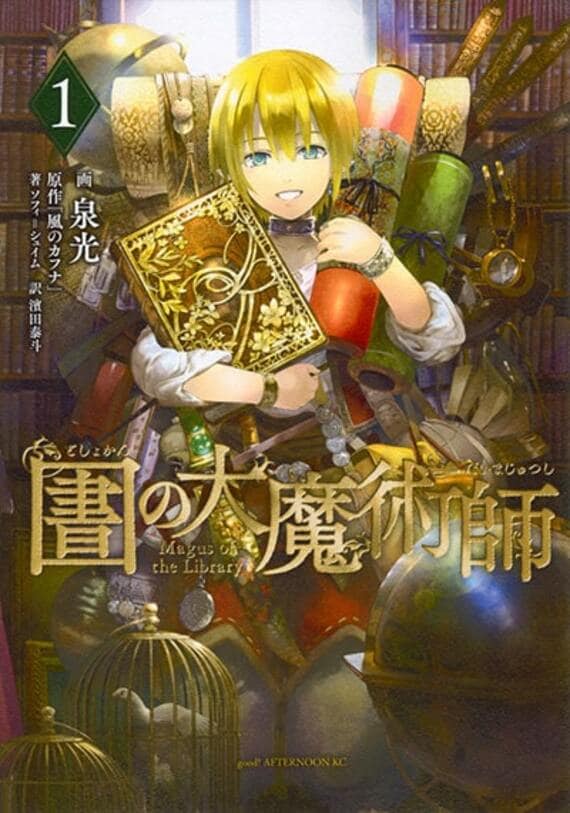
著/泉光






























