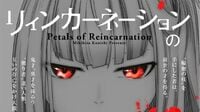髪型や服装「古い校則廃止」後に学校で起きたこと 奈良若草中の着地点「生徒の学ぶ権利を守る」

教職員を悩ませる「金髪で授業」問題に決着
近鉄奈良駅から徒歩20分、東大寺を望む多聞城の跡地にある奈良市立若草中学校。同校の教職員の間で、ある議論がそれまで以上に活発に交わされるようになったのは2018年のことだった。
その議論とは、「子どもの基本的人権を尊重する教育とは何か」というものだ。若草中学校教職員の間で伝統的に議論されてきたテーマだが、生徒指導のあり方を見つめ直す中で、改めて注目が集まった。同年、若草中に着任した栗山泰幸氏はこう話す。

奈良市立若草中学校 生徒指導主事
「以前から、関西の地方都市の生徒指導では、茶髪や金髪の生徒を卒業式などの式典や行事などに参加させていいのか、という議論がなされていました。服装や髪型によっては、その生徒をいったん帰らせるという学校もあります。しかし、私やほかの教職員も『髪型や服装はそんなに大事なのか?』という疑問を常々持っていました。一方で、1つ許すとずるずると何でも自由になってしまう懸念もあります。しかし、教職員によって基準や考え方もさまざま。そこで、教職員同士がいろんな意見や考えを出し合って見直しませんか、ということになったんです」
こうして、職員室のあちこちで、活発な議論が起こるようになったという。それを可能にした要因は2つある。1つは、同校が伝統的に人権教育に力を入れてきたこと。もう1つは、教職員の平均年齢が低く、固定観念にとらわれず、シンプルに疑問を出し合えたことだ。
もちろん、「中学生がピアスをする必要はない」という意見もあるが、栗山氏は「いろんな意見があっていい。大切なのは、教職員同士がいろんな思いを話し合うこと」と語る。そうして教職員の間で議論を重ねるうちに、1つの着地点が見えた。「生徒の教育を受ける権利を奪ってはいけない」ということだ。
「教育を受ける権利は憲法で保障されている。派手な髪やピアスをしている生徒がいたら、まずは教員が声をかければいい。髪色や装飾具を理由に、式典や行事、教室に入れるかどうかという議論はやめようということになったのです。すごくスッキリしましたね」
それが19年のことだ。栗山氏が同校の生徒指導主事に任命された年だった。20年には、靴下の色など古典的で細かい校則による生徒指導を廃止した。
「生徒指導には、教員の力量が問われます。生徒とうまくコミュニケーションが取れていたり、授業者として信頼や尊敬をされていたりすれば、生徒は素直に話を聞いてくれますし、信用されていなければ聞いてくれません。だからこそ、教員は逃げずに生徒と向き合い、指導することが求められるのです」
逆に、生徒と信頼関係をつくるために「お友達先生」になってしまう先生も中にはいる。子どもたちの都合や気分に流されて安易に迎合してしまう先生だ。生徒ともめることがなく、ある意味、楽で人気者になってしまうことすらある。
だが若草中では「いいことはいい! おかしいことはおかしい!」と、「当たり前のことを当たり前に伝え続ける姿勢をみんなでもう一度大切にしていこう」と教職員同士で話し合ってきたという。校則を守ることが教育の最終目標ではなく、生徒と向き合い、生徒の教育を受ける権利を守ること。教職員の間にある共通認識が、そうした指導を支えている。
校則廃止後に、みんなで考えた教室マナー
若草中では、細かい校則が書かれていた生徒手帳も廃止した。
「生徒手帳は1冊約500円です。生徒たちが読んでいると思えないのに、買ってもらう必要があるのかなと。一部には『わざわざなくす必要はあるのか?』という意見もありましたが、廃止に対する抗議はゼロでした。学割などを受けるために、生徒手帳の代わりにカードタイプの生徒証明を発行していますので、何の問題も起きていません。子ども主体の学校づくりをしよう。子どもたちの自尊感情と主体性を向上させようというところがいちばんの目標なので、教務部の了解もすぐに得られ、対応はとてもスムーズでした」