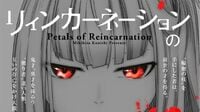髪型や服装「古い校則廃止」後に学校で起きたこと 奈良若草中の着地点「生徒の学ぶ権利を守る」
「私は自分の研究実践の中で『ほめ言葉のシャワー』(日本標準)で知られる菊池省三さんに出会い、影響を受けました。しかし、菊池さんのような達人のごとく、授業中に子どもたちを褒めて認めて、感謝するということをすべてやりきるということは、私にとってはまだまだ難しいものです。そこで菊池さんの下で学ぶ中で出会った、大分県教育庁別府教育事務所所長である山香昭さんの実践をアレンジし、生徒たちの学校生活の様子を記録に取り、その言動の価値や子どもたち一人ひとりの存在のありがたさを伝える『美点凝視』の掲示物を学校にあふれさせようと考えました」

最初は栗山氏が一人で始めた取り組みだったが、しだいにほかの教職員や生徒の間にも広がっていった。今では生活環境委員会の活動として、教職員や生徒同士が見つけた生徒のよさをポスターにして貼り出しているという。
「美点凝視を続けるうちに生徒の自尊感情も少しずつ上がってきているように見えますし、何より生徒が楽しみにしていて。月に一度ポスターが貼り出されると、生徒が集まってきて熱心に見ているんですよ。始めの頃は、私がたった一人で写真撮影をし、褒め言葉のメッセージを書き、掲示していましたが、今では生徒たちがそれぞれ各学級や委員会でタブレットを駆使して作成、掲示までしてくれています。多聞城跡と呼ばれるこの地を、いつか美点凝視であふれる『美点城』と呼ばれるようにしたい! 生徒たちとそんなふうに話しています」
この取り組みは、生徒が自分の気持ちを言葉にすることにもつながると栗山氏は考える。現代の子どもの中には、SNSやプライベートスペースでは別人のようにコミュニケーションが取れるのに、パブリックではなかなかできないという子がいる。ただ、そういう子も「SNSの中だけでずっとハッピー!」ということはないと栗山氏は話す。
「ほとんど多くの生徒が、周りの人との人間関係や家族関係の中でしんどさを感じています。いくらスマホやSNSなどの情報機器が発達しようとも、子どもたちは気の許せる友達が欲しい、自分のことを家族に認めてもらいたい、褒めてもらいたいといった生身の温かい人間関係を求めていることに違いはありません。子どもも大人も、結局は生身の人と誤解なく、笑顔で関わっていきたいと心の底では願っているように感じるのです」
また、この取り組みと併せて、生徒指導部からのお便りや集会で生徒に伝える話のあり方も見直した。生徒指導部からの話というと、どうしても注意や説教というイメージが強いが、生徒のよさや努力に目を向け、生徒同士で対話して互いに褒めて、認めて、感謝する場に変えていったのだ。
生徒指導の働きが、「問題行動への注意や叱責、保護者・地域住民からのクレーム対応」といった消極的で部分的なものから、より明るく積極的で、全体的なものになったのは、当事者全員が「いいことはいい! おかしいことはおかしい!」という当たり前のことを、当たり前に続けてきたからだと栗山氏は話す。
生徒も教職員も安心して発言できる環境を
今は、「リンゴが好きか、バナナが好きか」で世の中のあちこちでいさかいが起こる世の中だと栗山氏は指摘する。大人も子どもも毎日のように、互いの違いや欠点、失敗を認めずに非難し合っている。コロナ禍の中で、大人たちも心の余裕を失い、地域の子どもたちや学校を見る目にも、よりいっそうぬくもりが感じづらくなってきた。
「人それぞれ、好みや考えが違うのは当たり前のこと。その違いを尊重し合って、物事を進めていく手続きこそ平和で民主的なプロセスだったはずです。大切なのは、自分と違う考えの相手と尊重し合って話し合っていけるかどうか。生徒には、自分を守るために相手を否定や中傷する必要はないこと、人間関係は『違いや対立があってこそすばらしい』ということを知ってほしいのです。そのためにも、自分の意見を安心して言える土台や環境をつくりたいと考えています」