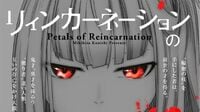髪型や服装「古い校則廃止」後に学校で起きたこと 奈良若草中の着地点「生徒の学ぶ権利を守る」
さらに、自転車通学の規定変更や性別によらない制服選択なども実現。1年生を中心に、自由に制服を着こなしているという。注目すべきは、こうした校則の見直しは、教職員と生徒が一緒に進めてきたこと。同校では各学級で出た意見を学年ごとに集約し、それを学校全体のテーマとして吸い上げるシステムになっている。
「生徒会と各委員会の代表が意見を集め、生徒指導主事の私と生徒会担当教員の2人が職員会の代表として教職員の意見を取りまとめたうえで、生徒会と職員会で議論を繰り返し、最終的に生徒総会で議決します。その決定を教職員がバックアップするという形です」
生徒会と職員会は対等な議論を行うが、生徒総会の決定が尊重されるため、生徒側の提案を実現する際のリスクは総会前に十分に議論・検討する。その際も、生徒会と職員会は対等な立場で議論を行うという。

昔ながらの校則が廃止されたとはいえ、集団行動には指針も必要だ。また、校区の小学校から「校則がない中学校生活について小学生にどう教えればいいか」という問い合わせもあった。そこで、生徒と教職員で1日の流れを見直す「若中生の一日検討委員会」を設置、学校生活の約束事(1日の流れ)をまとめた。身だしなみや欠席の連絡、教室の移動など、学校生活の1日の中で何に注意して過ごせばいいか書かれている。
「これは『学校生活の共通マナー』のようなもので、守らなかったからといって罰則があるわけではありません。気づいたことがあれば、その都度話し合えばいい。今は、カーディガンの着用について話し合っています。私なりに校則の歴史について調べたら、校則は、もともと生徒会会則として誕生したようです。本来は生徒や教職員、保護者や地域の人々の間の共通認識・共通マナーとして誕生したものが、いつの間にか『学校に押し付けられるもの』として認識され、固定観念となったのではないでしょうか」
「いいことを伝える」美点凝視で生徒に変化
しかし、中学生が教職員と対等に議論を行うには、それなりの力量が必要だ。自分で考える力やそれを言葉にまとめて伝える力、相手の主張を理解する力を総合的に使いこなす力が求められる。若草中に、そうした力を養うための取り組みがあることが注目すべきところだ。
1つ目は、いわゆる「青年の主張」だ。各学級、各学年で選ばれた代表が自分の訴えを学校全体に向けて主張する。これを伝統的に実施しており、自分の言葉で伝えるという積み重ねが行われてきた。2つ目は授業のあり方だ。
「若草中では、私が赴任するずっと前から『人権教育を学校の柱にしていながら、教員ばかりがしゃべる教師主体の授業でいいのか?』が教職員の間で議論されてきました。そこに新学習指導要領で『主体的・対話的で深い学び(いわゆるアクティブ・ラーニング)』の実現が求められるようになり、これまで以上に生徒にスポットライトを当てる時間を増やし、自分の思いをアウトプットする力を高めようという機運が高まったのです。
教務主任や学習部長が、熱心に職員研修や研究授業を計画したおかげで、教科の枠組みを超えて、教員同士が授業の腕を高め合う風土が学校全体に広まりました。管理職の教員も、授業の様子を毎日のように見に行き、その都度子どもたちや教員の頑張りを認め、前向きな助言をしています」
今では、ほぼすべての授業で「Quizlet」や「Kahoot!」などの学習クイズソフトで知識理解の徹底を図るとともに、Google Classroomやロイロノートで意見の共有やプレゼンテーションをするといったICTを適切に活用した確かな学力の育成にも取り組んでいるという。
そして3つ目は美点凝視だ。美点凝視とは、生徒のいいところ、見習うべき姿勢をポジティブな言葉で伝えていこうというもの。