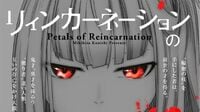髪型や服装「古い校則廃止」後に学校で起きたこと 奈良若草中の着地点「生徒の学ぶ権利を守る」
だからこそ、保護者や地域住民などの大人も、自分の好みや考えだけを子どもたちや教職員、学校に押し付けず、対等な立場で民主的に対話ができる関係性を大切にしてほしいという。大人が、相手を尊重し合って話し合ったり、考えの違いをもとに不毛な争いをせずに譲り合ったりできる姿が、子どもたちにとって最も豊かな教育環境になると考えているからだ。
校則を見直し、新たな約束事を話し合ったことは、まさにその表れだろう。同校の取り組みが目指したのは、単に古い校則を廃止するということではない。教職員と生徒が気持ちや考えを自分の言葉で話し、互いに尊重し合うそのプロセスに価値があるのだ。

今の課題は、こうした取り組みが「生徒会役員がやっていること」を「他人事」と感じてしまう生徒もいること。生徒会もその点は意識しており、自分たちが学校をつくることの意味を積極的に広報しているという。
「生徒たちには『自分事』として考えてもらい、それを自信にしていってもらいたいですね。本校の取り組みは、決して派手なものでも、突発的なトップダウンでなされたものでもありません。卒業生や先輩教職員が守り続けてきた『子どもの基本的人権を尊重する教育』の先に、新たな議論や対話を地道に積み重ねてできたものです。生徒も教職員も、一人ひとりが学校生活の主人公として自分の思いを真っすぐに伝え合う中で、喜びや苦しみを共有しながら地道に前に進んできました。しかし、それでも学校は大きく前に進む、明るく前向きに変われることがある!と自信が持てました」
こう栗山氏が話すのには理由がある。学校現場の閉塞感だ。今もコロナ禍で苦労や悩みを抱える教職員は多いが、以前から学校現場は明るい話題が少なかった。教員採用試験の倍率低下は、その象徴だ。新しい教育が次々と導入される中で組織の連携や体制の強化が求められる一方、「教職員一人ひとりの個性や感性が認められず、教育や子どもたちに対するそれぞれの思いを発信しづらい世の中になった気がしてならない」(栗山氏)と言う。だからこそ、地方の公立中学という若草中の取り組みを知ってほしいと。
学校や教育に対する思いを一人ひとりが当事者として積極的に発信することが、新しい学校づくりや教育が生まれる原動力になるということだろう。「私立だからできた」「都会の学校だからできた」「あの先生がいたからできた」ではない。見て見ぬふりをせずに目の前のちょっとした疑問について考えてみる。そこから学校は変われるということだ。それは教職員が自信を取り戻す、諦めを希望に変える一歩なのかもしれない。
(文:吉田渓、写真:すべて栗山氏提供)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら