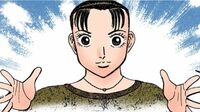これは僕もすごいなと思っていますが、子どもたちはシビアに掃除結果を自己チェックし、ズルをすることがないんですよ。また、このマップは、勝ち負けを競うのではなく、参加者全員で協力しながらゴールを目指す「協同ゲーム(コーポラティブゲーム)」の形を取っています。
例えば、ゴミモンに勝つと「サイコロを2回振れる権利」などのアイテムも得られ、そのアイテムはほかのチームにあげることもできる。そういったアイテムも使いながら力を合わせてゴールを目指すのが面白いようで、みんな楽しそうに掃除するようになりました。
――ゲーミフィケーションを取り入れるうえで気をつけたいことはありますか。
狙いは、「子どもたちの自立・自律を促す」こと。ゲーム化する際に加える要素を、全員が理解できるようにする配慮は欠かせません。子どもたち自身でルールを改訂していくような、当事者意識を生み出す工夫を心がける必要もあるでしょう。
また、「報酬が目的になってしまうのでは?」とよく言われますが、確かに報酬の与え方には注意が必要です。これについては、報酬を活用した実践「トークン」のご紹介とともに、次回詳しくお話ししたいと思います。

1978年生まれ、北海道出身。東京都の公立小学校教員として14年間勤務。2016年、主に病気休職の教員の代わりに担任を務める「フリーランスティーチャー」となる。これまで公立・私立合わせて延べ11校で講師を務める。NPO法人「Growmate」理事としてマーシャル諸島で私設図書館建設にも携わる。近著に『マンガでわかる!小学校の学級経営 クラスにわくわくがあふれるアイデア60』(明治図書)
(写真:田中氏提供)
(注記のない写真はiStock)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら