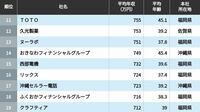「つまらない風習」と東村さんは一刀両断するが、一方で、教員の狭い世界で生きていくには、「受け入れざるを得ない現実」だとも話す。
「男性教員は、部活の顧問をしていないと、管理職からの信頼を得られないのが現実です。夫の学校の校長は運動部の顧問を持っていましたし、夫も将来は校長になりたいと思っています。ですから、当時まだ交際中だった夫から『打診を受けた』と相談されたとき、断ってくれとはいえませんでした」
東村さんは心情的には夫に理解を示しながらも、現実の理不尽さには納得できないという。切実だと打ち明けるのが妊活の問題。それはそうだろう、このままでは妊娠から出産、育児まで“ワンオペ”になることは確定的だ。
「子どものため」のやりがい搾取が横行
夫を苦しめる部活、妊活にも自由に取り組めない現状。理不尽なことばかりで、「学校には歪んだ常識がある」とまで言い放つ東村さんだが、教員の仕事にはやりがいを感じているとも語る。どうやら、そこに問題の本質はあるようだ。
「子どもと一緒に勉強するのは本当に楽しいです。できなかった問題ができるようになったり、意地悪ばかりしていた子が優しい言葉をかけられるようになったりと、成長が目に見えるのが教員の醍醐味ですし、何物にも代えがたいと思っています。子どもたちのことを考えると『こうしてあげたい、ああしてあげたい』といろいろなアイデアが浮かんできます。でも、それをすべて実行できるかどうかは、別の話です。年配の先生に多いんですが、『子どものため』を免罪符に仕事をどんどん増やしてしまうんです。この言葉を盾に仕事が増える風潮はもう終わりにすべきですし、結局部活もそういう考え方の延長にあると思っています」
部活で「100日連勤」はどう見ても異常であり、前出のように文部科学省も部活から教員を切り離そうとしている。それでもその動きは遅々として進まない。
「私は、そんなに大それたことを求めているつもりはなくて、プライベートを少し充実させたいだけです。私はもう半分諦めましたけど、このままでは教員のなり手がいなくなってしまうのではないかという危機感があります」
プライベートに不安を抱え、連日の激務に疲れ果てた教員が、子どもたちの健やかな成長を支えるという構造には無理がある。「部活の顧問」という存在は過剰なサービスで成り立ち、そのことで先生の心身がむしばまれている――そんな状態は、子どもたち自身も決して望んでいないのではないか。
(写真は投稿者提供)
※プライバシー保護のため、特定の個人を識別することができる情報を一部置き換えて掲載しております。
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら