どう乗り越える?「学校のICT活用」の高いカベ 突出を許さない公立、進学実績を重視の私立

iTeachers(アイ・ティーチャーズ)とは、小学校をはじめ中学校、高校、大学、専門スクール、学習塾まで、公立・私立や学校種を問わずさまざまな先生が集まる団体だ。2013年という早期から、それぞれの現場でICTを活用した教育を実践し、「新しい学び」を共有、提案してきたつわものたちがそろう。
今回集まってもらったのは、茨城県古河市立諸川小学校の薄井直之先生、佐賀龍谷学園龍谷中学校・高等学校の中村純一先生、大阪大学サイバーメディアセンター教授の岩居弘樹先生、大手学習塾に勤務しながら、教育ICTコンサルタントとして活躍する小池幸司先生の4名。
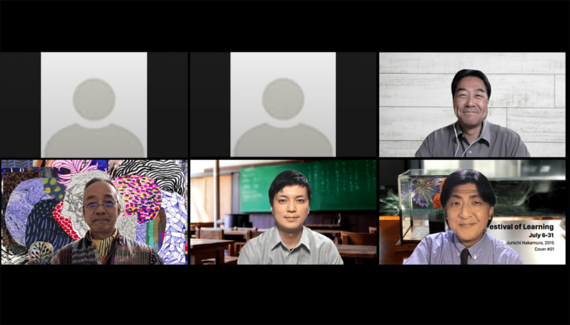
前編(現役先生に聞いた「学校のICT活用」の進み具合)では、たとえ同じ市内、同じ学校であってもICTの活用度合いには違いがあること、先生のICTに対する意識やスキルにも大きな差があることが、先生方のリアルな話を通じて実感できた。ただ、全員が「ICTによって子どもは予想外の能力を発揮する」と話し、「先生は一方的に教えるのではなくファシリテーションすることが大事」ということだった。後編では、それぞれの学校現場における課題と、それを克服する方法を探った。
「すべての先生ができないと却下」も珍しくない
――教育現場でICT活用を進めるうえで、どのような課題がありますか。
小池 公立学校では、ICT活用を積極的に推進していても、それを主導した先生が異動してしまうと、揺り戻しが起き、途端に取り組みをやめてしまうこともあります。ICTに後ろ向きな先生も多い中で、先生個人よりも学校、自治体として、いかに取り組みを進められる体制を築けるかが大きな課題だと思います。

大手学習塾で講師、広報・IT責任者を歴任。同社でのiPad導入を機に公教育にICTを広めようと、ライフワークとして教育ICTに関する情報発信を始める。YouTubeチャンネル「TDXラジオ」を開設し、新しい学びと先生の働き方改革をテーマにした番組「Teacher's [Shift]」を配信している(画像提供:iTeachers)
薄井 昨年の一斉休校当初、当時担任をしていたクラスの児童たちから「家にPCやタブレットがない子には学校の端末を貸し出せば、Zoomでオンライン授業ができるし、ロイロノート・スクールで課題提出もできます」と提案され、上司と相談しましたが、「すべての先生、学校が対応できるわけではないから」と却下されました。Flipgrid(※1)などの教育向けアプリは、一般にあまり知られていないせいか、利用を申請しても、なかなか教育委員会の承認が下りないのも悩みです。






























