どう乗り越える?「学校のICT活用」の高いカベ 突出を許さない公立、進学実績を重視の私立
薄井 タブレットが1人1台配備されることになり、市教委もICTの活用事例を紹介していますが、先生たちのICTスキルを一気に高めることは難しい課題です。そこで、まずは、子どもから聞かれてわからないことがあれば、相談できる教員間の情報ネットワークの構築が大事だと思います。
オンラインでつながれば、学校間の壁も取り払われるので、質問した児童と、それに答えられる別の学校の先生を直接つなぐことも可能になるはずです。学校間の交流など、できることから始めて、先生たちの不安を除いていって、教育ICT環境を先生たち、子どもたちが一緒に楽しめるようにしていけたら、と思います。

2020年4月から現職。6年生の担任、学年主任、情報教育主任。古河市のICT支援推進委員(旧ICTエバンジェリスト)。ICT機器を活用し、朝の会で児童が自分の考えを発表する機会を設けるなどの実践に取り組む。「子どもたちの声を聞くのが好き」(画像提供:iTeachers)
岩居 テクノロジーは皆さんの想像以上に進んでいて、先生たちがやりたいことは、大抵できるようになっています。例えば、音声やビデオで解答するスタイルのテストなら、オンラインでもある程度不正行為を防ぐことができるのではないでしょうか。そのためのツールはすでにあります。先生方には、マインドセットを切り替えていろいろな可能性にチャレンジしていただきたい。
私はオンライン授業をサポートするために「Zoom+α」(※3)の相談会を始め、学内だけでなく学外の先生からの相談もたくさん受け付けています。オンラインで何ができるかが明確になると、対面授業で大事にすべきことも見えてくると思います。
※3 ビデオ会議システムのZoomや授業支援クラウド、ロイロノート・スクールなどを使った遠隔授業のやり方を紹介している(https://zoom.les.cmc.osaka-u.ac.jp/)
中村 まずは、少しでも教育にテクノロジーを取り入れ、学びが楽しくなる感覚を子どもたちと一緒に味わってほしいと思います。体験すれば、断片的な情報から「ICTは危険で、子どもに使わせるべきではない」と考える先生にも、学びを変えられる可能性に目を向けてもらえるのではないでしょうか。
コロナ禍で、子どもたちの社会への関心は以前より高まっています。紙と鉛筆以外にICTツールも使えば、子どもたちが考えた社会課題の解決策をバーチャルなモデルで提示することもでき、世界に発信することができるのです。子どもたち自身が世の中の役に立とうとする取り組みを、学校、教育関係者にも支えてほしいと願っています。
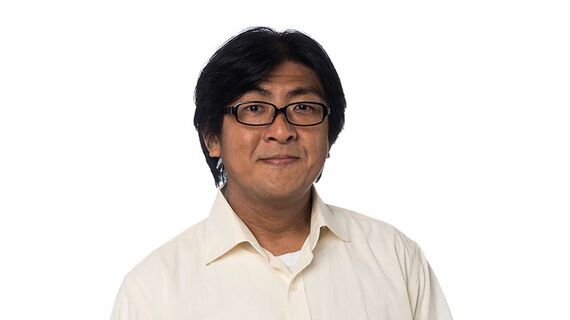
公立中学校勤務だった2013年ごろから教育へのテクノロジー導入の実践を重ねてきた。20年4月、iPadを使った教育にいち早く取り組んできた佐賀龍谷学園龍谷中学校・高等学校へ。「これまでの考え方や限界を打破して、子どもたちを中心に据えた教育を目指したい。 VRやARなどのXRテクノロジーに興味あり」。Apple Distinguished Educator(画像提供:iTeachers)






























