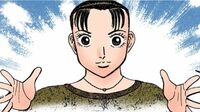小中学校「30人学級」人数減の本当の意味と効果 少人数学級30年ぶりに議論が動き出したワケ
今、少人数学級を導入する意義として、大きく3点が挙げられている。
1つ目は、コロナをはじめとする感染症対策だ。文科省がまとめた「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」は、人との間隔について、感染レベルの低い地域は「1メートルを目安に最大限の間隔」、高い地域は「できるだけ2メートル程度(最低1メートル)」空けるよう求めた。平均面積約64平方メートルの教室に40人いると、1~2メートルの間隔を空けるのは難しく、学級を2グループに分けて分散登校にするなどの対応が取られたケースもあった。

2つ目は、児童生徒一人ひとりに注意が行き届きやすく、学習面や生活面で、きめ細かな指導ができ、教育の質の向上が期待できる点だ。コロナ禍で必要性が痛感された学校のICT化のため、高速大容量通信ネットワークや、小中学校の児童生徒に1人1台の端末を行き渡らせる環境を整備する「GIGAスクール構想」の効果を高めるためにも少人数学級が必要と、ワーキンググループで指摘されている。
教育再生実行会議で、有識者として意見を述べた千葉県南房総市教育委員会教育長の三幣貞夫氏は「コロナ禍に先立って、昨年秋の台風による家屋損壊や大規模停電・断水に見舞われた南房総市では、心に傷を負った子どもが多くいた。市内では小中学校の7~8割の学級は30人未満になっているが、30人以上の学級では、一人ひとりの表情に注意を払い、声をかけるのは困難になるというのが、現場を回ってみた私の感想だ。学級は生活の集団でもあり、子どもの視点で先生との間に1対1の関係を築くことが教育には重要」と話す。
そして3つ目は、小学校で3割超、中学校で6割近くが過労死ラインに達するとされる、教員の長時間労働の軽減だ。
少人数学級の効果に懐疑的な声が多い理由
しかし、少人数学級の効果には懐疑的な声も根強い。全国で学校が本格的に再開し始めた6月1日から8月31日までに、小学校の児童428人、中学校の生徒266人の感染報告があった。しかし、判明した感染経路は家庭内感染の割合が高く、校内での感染は、児童9人(2%)、生徒18人(7%)にとどまる。
2009年の新型インフルエンザは学校での感染が問題になったが、今のところ、学校での新型コロナ感染は抑えられている。また、少人数学級移行には、数年単位の期間が必要だ。過去の定数改善は、実施までに5年から12年かかっていて、完了時には感染が終息している可能性もある。逆に実施を急げば、短期間で大量任用される教員の質の低下が懸念される。