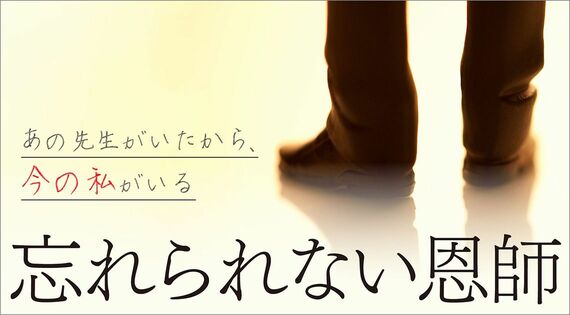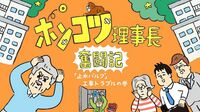「『分人』とは、状況や場所によって生じる複数の人格のことです。1クラス30人全員に対して一本調子で話されても、伝わりにくいですよね。『この子はこういう話し方じゃないと通じない』というのがあると思いますし、そうやって接すれば子どもの側も先生を信頼できるようになるでしょう」
もちろん、実践している教員もいるだろう。しかし、制度や教育現場の同調圧力などが阻害している実態もあるのではないかと平野氏は指摘する。
「初等教育は、多様な人間が集まってコミュニティーを形成するために、共通の言語や計算方法を身に付けさせるわけですが、それが『同一性』の確認手段にすり替わってしまって、その感覚が中学、高校とずっと続いている気がします。例えば、ツーブロックの髪型を禁止する都立高校の校則が話題となりましたが、髪型を規制することの教育的な意味はどこにあるのでしょうか」
そうした同一性の強化と多様性への理解度の低さは、最近問題となっているインターネット上の誹謗中傷や、対話をすることではなく「言い負かすこと」に重きを置く風潮にもつながっているのではないか、と平野氏は指摘する。
裏を返せば、「どう生きるか」を安心して考えられる、多様性が保証された環境を整えることが、一人ひとりの主体性や能力を伸ばすことにつながるともいえる。
「今は、これだと将来安泰という道がまったく見えなくなってしまっているので、教育はすごく大変だと思います。その中で、生徒がいろいろなものにオープンに受け入れて、挑戦して、失敗しても柔軟に受け止めてまた挑戦して、というふうにバランスをとってうまく生きることができるような教育だといいなと思います」
「小説家」というある種“特殊”な道に進もうと打ち明けたとき、小野教授は軽やかにそれ受け入れたという。芥川賞受賞作の『日蝕』が、文芸誌に一挙掲載という異例のデビューを飾ったが、平野氏はゲラ刷りの段階で小野教授に読んでもらった。
「小説を書いていることは全然伝えていなかったので驚かれました。一方で、私が小説の道を歩もうとしていることに対しては『卒業してサラリーマンになるわけじゃないと思っていた』というようなことをおっしゃって、理解を示してくださったのはうれしかったです。その後も作品を送れば必ず読んでくださって、感想をいただいたり励ましていただいたりして、とても心強かったです」
正解のない大海原で迷っていた平野氏にとって、小野教授がかけてくれた言葉が、不安を打ち消して創作に邁進する追い風となっていた。「どう生きるか」。その深い教えは作家としてだけでなく、今を生きる一個人としての羅針盤でもあった。
「私にとっての『恩師』は、人生の方向が、その出会いによって変わって、よい形で大きな影響を及ぼした存在です。ほかにもお世話になった先生はたくさんいますが、私にとっては小野先生がやはり恩師だなと思います」
制作:東洋経済education × ICTコンテンツチーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら