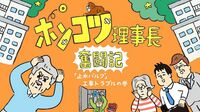「ヨーロッパの思想や哲学というのはかなり遠い世界のはずなのですが、自分自身の出来事としてすごく響いてきました。例えば、古代ギリシャの話が印象に残っています。アテネは戦争や疫病に見舞われ、人々は精神的な危機を迎える。賢人とされていたソクラテスが処刑されてしまい、その弟子のプラトンは哲学的な思索を始める。西洋の哲学はそういった危機意識から始まっています。思想家たちが当時の社会をどう捉え、自分の思想を練り上げていったか、小野先生が非常に鮮やかに、迫力をもって語られていて、衝撃を受けました。90年代当時の日本の閉塞感やニヒリズムに通ずるところがある、とも感じました」
ヨーロッパの思想家たちが何を残したか、知識として伝えるのではなく、当時の状況を踏まえたうえで「どう生きたか」を示す講義。それは、社会に対してどのように立ち向かい、解決のための思索を積み重ねていくプロセスを、学生に共有させる営みでもあった。だからこそ、社会の閉塞感を感じ取って「どう生きるか」を模索していた平野氏に共鳴したのだろう。
恩師に学んだ「矛盾と複雑さを受け入れる」姿勢
小野教授によって示される思想家たちの生き方は、平野氏の物事の見方にも大きな影響を与えた。
「粗雑に、断定的かつ一面的に何かを見てはいけないということを小野先生に学びました。1人の思想家でも時期によって思想の変遷があり、それが矛盾している場合もある。1人の生き方の中でも多様な可能性と変遷があります。複雑な物事は、たとえ矛盾していたとしても、複雑なまま見るべきだ、と教えられたのはとても貴重でした」
変わりゆく環境の中で、誰もがいろいろな事情を抱えて生きている。時には矛盾した考えを持つ場合もある。平野氏は、自らの実体験と小野教授の教えを照らし合わせてそのことを理解し、「多様性と自由」を拡大していった。
「私は大学に入学するまで九州の田舎にいて、狭い世界しか知りませんでしたが、バンドを組んだり、大学近くのバーでバーテンダーのアルバイトをしたりして、いろいろな世界を知ることができました。そうした生活を経験しながら、一方では小野先生の講義やゼミで、自分が接している多様な現実を包摂できる思想の枠組みを学べたことで、自分が生きている現実を理解できたと思っています」
もう1つ、小野教授にまつわる思い出として平野氏が「自分を変えた」と語るのは、若者ならではの恥ずかしい体験だった。小野教授のゼミに入ってすぐ、意見を求められた平野氏は、当時読んでいた思想家の書物の内容をそのまま述べてしまう。ズルをしようという意図はなく、共感したことを口にしただけだったが、小野先生にどの書物からの引用なのかを即座に見破られる。
「得意げに話していた自分が穴に入りたいほど恥ずかしく、思想を語るにはこれではいけないと思いました。当時は自分の言葉で語れるような教養もなかったのですが、洗練されていなくてもいいから、自分で実感と共に練り上げた言葉を語るべきだとつくづく感じました。同時に、小野先生は学問の世界でも『勉強しすぎ』といわれるくらいの碩学(せきがく)でしたから、安易に不勉強のまま『これが僕だから』でもダメで、もっともっと勉強しないといけないと深く反省しました」
支えとなったデビュー前の「恩師」の一言
大学3年生になって「恩師」と出会えた平野氏。2人の小学生の父となった今、教育に対してどのような思いを持っているのだろうか。そう聞いたところ、自身が提唱する「分人」の概念を通じて、初等教育の現場でもそうした多様性を認める教育をしてほしいと語ってくれた。