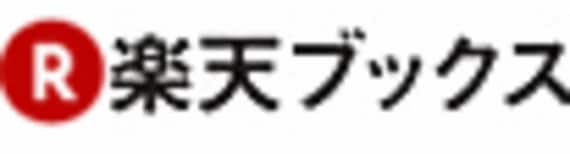戦後史の正体 1945−2012 孫崎享著

歴史研究において「陰謀史観」や「謀略史観」は世に尽きないが、本書は「米国の意向」「米国からの圧力」を軸に、日本の戦後史を前半期中心に解明した。
敗戦から占領の10年は自ずと「対米追随」路線が跋扈(ばっこ)する。それでも、重光葵や芦田均、鳩山一郎、石橋湛山、それに岸信介といった「自主」路線を描こうとする政治家が出た。冷戦は、日本をソ連との防波堤と位置づけさせ、講和条約による独立、日米安保条約も、その裏付けに使われた。
1960年代に日米関係は黄金期を迎え、高度経済成長が安全保障の問題を棚上げさせた。繊維問題をはじめ通商摩擦が頻発したが、追随路線に揺るぎはなかった。冷戦終結後、日本は再度「最大の脅威」と位置づけられたものの、唯一の超大国への協力を続け、現在に至っているという。
政治に比べ経済・通商面の分析に弱いうらみはあるが、「追随」と「自主」が濃淡を織り成す実相描写は、なかなか示唆的だ。
創元社 1575円
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら