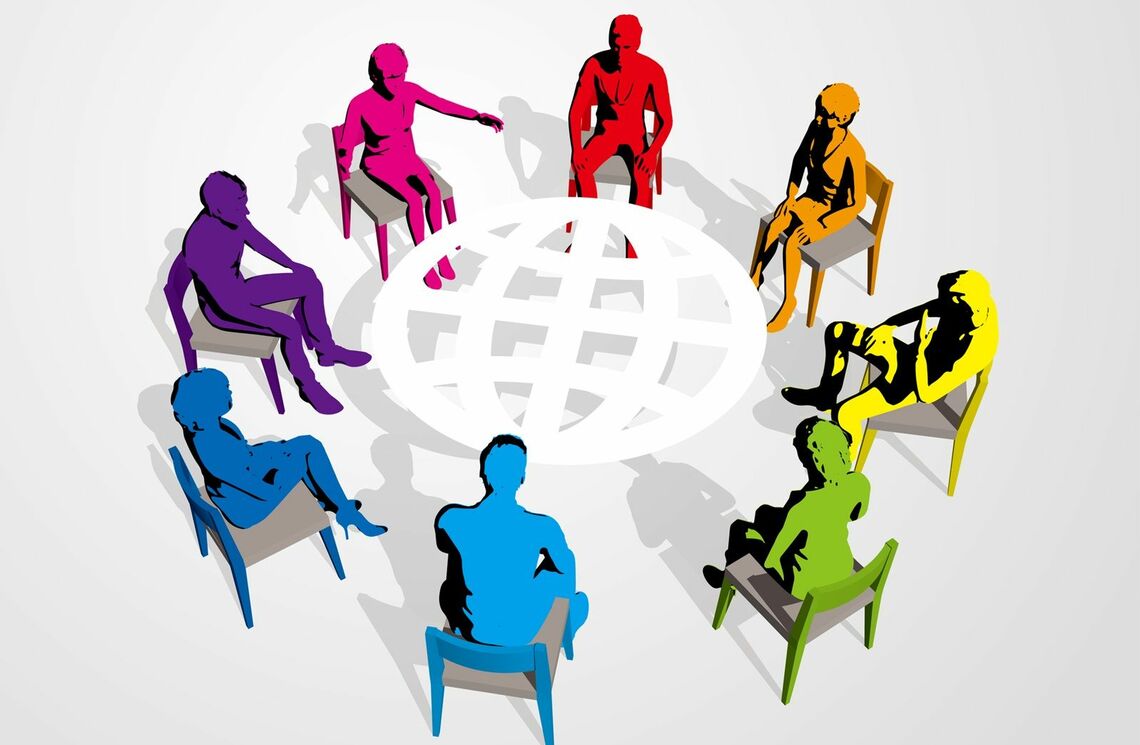
Aさん:情報・通信(40代)
Bさん:サービス(60代)
Cさん:コンサル(40代)
Dさん:元製造業(50代)
Eさん:広告(60代)
Fさん:非営利(40代)
Gさん:金融(50代)
進行:岸本吉浩(東洋経済編集部)
――国連は7月14日にSDGsに関する報告書を発表しました。ここでは、目標のうち35%が進展している一方、約半数は停滞、残りは後退していると評価されています。皆さんは企業やNPOなどの活動を通じ10年間、いわゆるSDGs・サステナリビリティに取り組んでいらっしゃいますが、現在はどのような状況とお考えでしょうか。
Aさん:SDGsが出てきた当初は、「これは重視すべき課題」と認識し、自社の企業サイトにも自社の考えや取り組みを載せていました。ただ、最近はあまり意識していないのが正直なところです。
Bさん:EV(電気自動車)がよい例です。一時は世の中からガソリン車が一掃されるような勢いでしたが、今はトーンダウンしています。新型コロナウイルスの発生やロシアのウクライナ侵攻、アメリカのトランプ大統領就任など、相当な逆風にさらされているのが現状です。欧州勢は「トランプ大統領がいなくなればもう一度戻る」と思っているかもしれませんが、私は「世界的にSDGsは忘れられた」という気もしています。
日本の国民性が不利になる
ただ、日本はまじめにコツコツと取り組む国民性です。企業の情報開示でも諸外国の企業が形だけにとどめるのに比べて、きっちり対応し続けていると思います。あるESG関連の勉強会で技術系の方から「環境関連にまじめに取り組んでいるのは日本だけで、このままでは不利になる」と聞いたことがあります。
実際、社内にも逆風が吹いています。以前はCSR(企業の社会的責任)やESG関連の部署が情報収集や対外発信、レポート作成などを担当していましたが、これらも経営計画や事業計画にビルトインされるようになりました。よくなった部分もありますが、逆に企業価値をどう上げるか直接的に説明がつきにくい社会貢献的な分野は大きく縮小せざるをえないなどの影響が出ていると感じます。



































無料会員登録はこちら
ログインはこちら