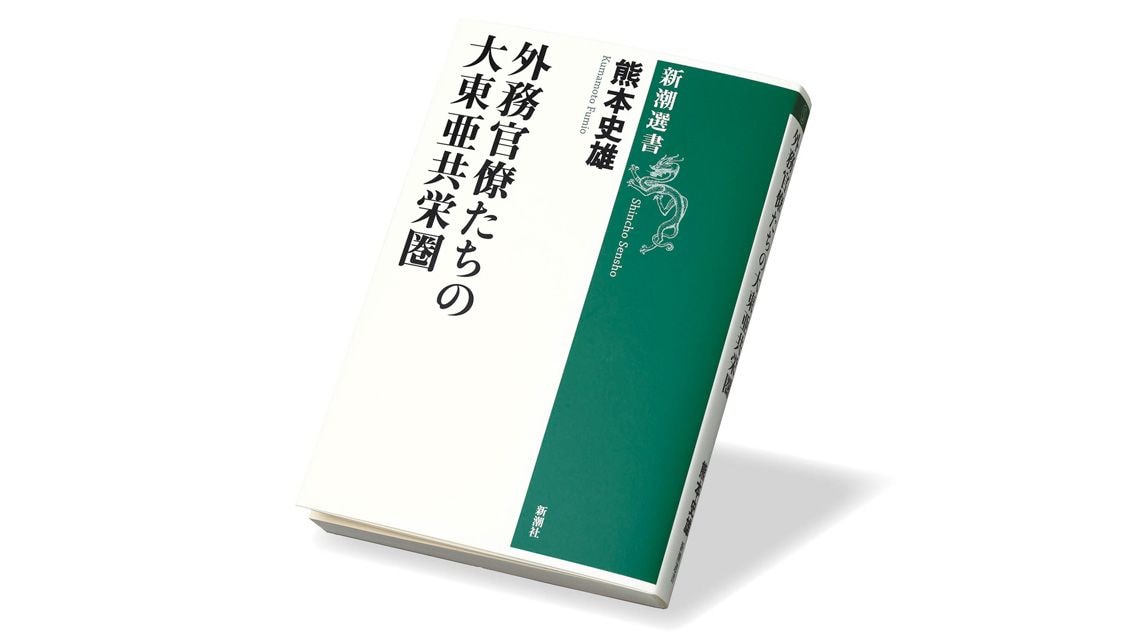
外務官僚たちの大東亜共栄圏(熊本史雄 著/新潮選書/1980円/304ページ)
[著者プロフィル]熊本史雄(くまもと・ふみお)/駒澤大学文学部教授。1970年生まれ。筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科中退。博士(文学)。外務省外交史料館外務事務官などを経て現職。専門は日本近代史、日本政治外交史、史料学。著書に『大戦間期の対中国文化外交』『幣原喜重郎』など。
太平洋戦争敗戦から80年。あの戦争は何だったのか。侵略だったのか、自衛戦争だったのか──議論は落ち着くどころか政治的意図を持つ暴論を含めて喧(かまびす)しい。
本書は膨大な史料の分析によって、外務官僚が「大東亜共栄圏構想」を生み出したことを論証する。小村寿太郎・幣原喜重郎・重光葵ら、ベスト&ブライテストであった外交官がなぜ大東亜共栄圏という悪手への道を開いたのか。あの戦争の意味をあらためて考えるには格好の一書だ。
地域概念「東亜」の誕生
日露戦争で、日本は南満州を勢力圏とした。その後、東部内蒙古を加えた「満蒙」は重要な権益となった。一方、対英米協調も重大な外交目標だった。外交官にとって、両立させがたい2つの崖上の稜線を行くが如き難行となった。
トピックボードAD
有料会員限定記事



































無料会員登録はこちら
ログインはこちら