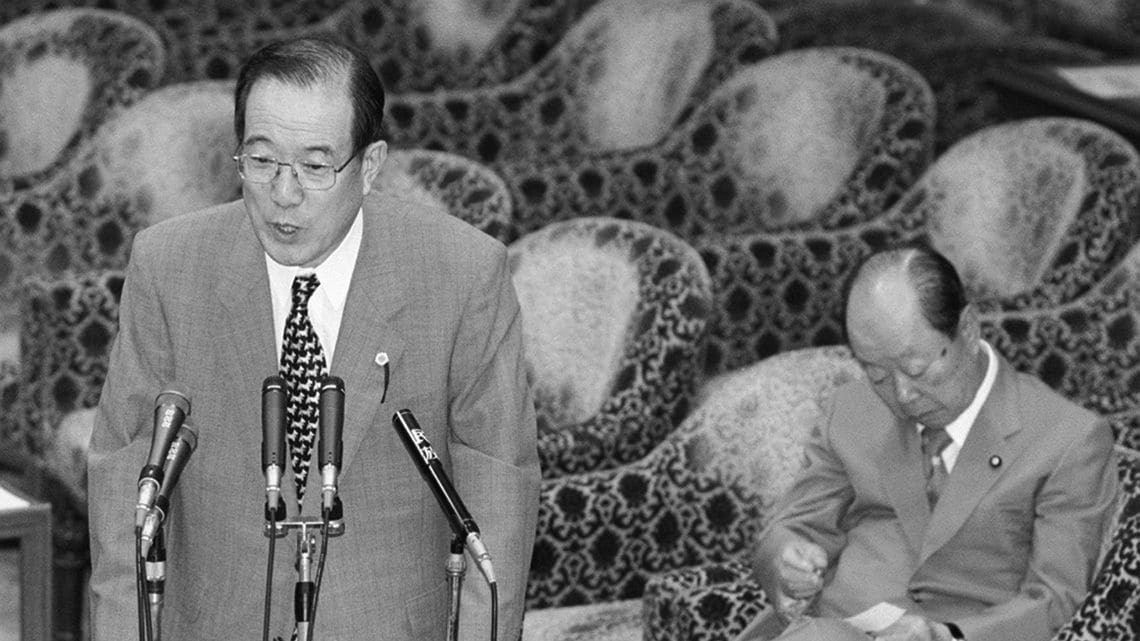
危機に直面した日本長期信用銀行をめぐる国会での与野党対立を解いたのは、公的資金投入を認めないとする野中広務官房長官の発言だった。「一か八か」の判断により野中が野党案を“丸のみ”したことで、長銀は住友信託銀行との合併を断念し、「特別公的管理」と呼ばれる一時国有化を選択せざるをえなくなった。
野中が野党案をのんだのは、衆参ねじれ状態の中で小渕恵三内閣を守るためだったが、実は長銀の「デリバティブ(金融派生商品)問題」にけりがついたことも大きかった、と関係者は明かす。
長銀が抱える金利スワップなどデリバティブの想定元本は、9月時点で50兆円近く残っていた。もし長銀の一時国有化がマスター契約上の「デフォルト」に認定されると、デリバティブは強制的に一括清算され、海外市場で不測の事態を引き起こす危険性があった。大蔵省や日銀が住信との合併を後押ししたのも「日本発の金融危機」を防止するためだった。
だが、合併交渉が難航する中、金融監督庁と日銀は国際スワップ・デリバティブ協会(ISDA)と折衝を重ね、9月下旬、「一時国有化はデフォルトに当たらない」とのお墨付きを得る。野中が舵を切れたのもこのおかげであり、監督庁幹部は「実はISDAが最大のヤマだった」と話している。


































無料会員登録はこちら
ログインはこちら