99年、深刻な経営危機に陥った日産へ仏ルノーから送り込まれたカルロス・ゴーン氏は赴任から数カ月でリバイバルプランを策定。村山など国内5工場の閉鎖や、従業員2.1万人と部品サプライヤー数5割の削減などの目標を掲げ日産を短期間で復活させた。
コスト削減で辣腕を振るったゴーン氏は再建後に拡大路線に転じた。ターニングポイントとなったのは11年6月に発表した6カ年の中期経営計画「日産パワー88」。世界シェア8%と営業利益率8%の目標をぶち上げた。販売目標は明言しなかったが前提から算出すると720万台。生産能力800万台を目指し、インドやロシアなど新興国へ工場を新設していった。
11年にCOO(最高執行責任者)を務めていた志賀俊之氏は、「世界中に工場を造ったが、その後に閉めた工場はわずかで過剰生産能力が今も日産を苦しめている。現役の従業員や取引先に申し訳ない」と後悔を語る。実際、十分な競争力を持つ新車を投入できず、インセンティブ(販売奨励金)の積み増しで17年度の577万台まで販売台数を引き上げたものの、無理な安売りによって日産ブランドはむしばまれていった。
拡大戦略が裏目に
18年のゴーン事件でカリスマ経営者が退場すると、無理を重ねた弊害が表面化する。

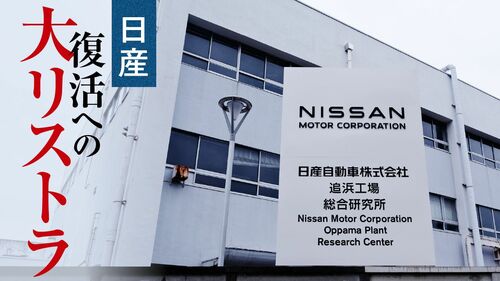































無料会員登録はこちら
ログインはこちら