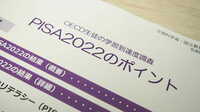北欧で「教科書"紙に回帰"」、「デジタル教科書推進」の日本はどう受け止めれば? フィンランドも異変、学習や健康面から議論
実はフィンランドでも、「何がデジタル化に適していて、何が適していないか」という議論は活発に行われてこなかったのだが、同調査はこの問題にもチャレンジしている。例えば、生徒を対象とする調査では、デジタル化の効果について、母語と数学については肯定的であった一方、物理と外国語の学習では芳しくない状況にあることが報告されている。
とはいえ、その結果をそのままデジタル化の適不適と結びつけて議論するのは、短絡的だ。同調査は、紙かデジタルかという議論以前に、教育現場がデジタル教材やデジタル環境のポテンシャルを十分に生かしているとは言い難い実態についても指摘している。今後、デジタルの教育的効果を議論するには、デジタル教科書のポテンシャルを生かす教授法の開発や教員の力量形成、学習環境の整備や支援体制の構築も必要になるだろう。
前述の通り、デジタル教科書をめぐっては、学習成果への影響のみならず、生徒の心身双方の健康やウェルビーイングの観点からも議論が行われている。例えば、増加するスクリーンタイムの問題に加え、デジタル機器の利用によりストレスを感じる生徒が一定数存在することも指摘されている。
こうした動向を日本はどう受け止めるべきか。フィンランドの事例は、紙かデジタルかという二項対立的な議論を超え、それぞれの利点を生かす方策を検討する必要性を示唆している。学校種や年齢、教科等の特性、適切な量やバランスなど、デジタル化の「用法と用量」の検討を通じて、子どもたち1人ひとりにとって最適な学習環境の構築を目指すこともその1つだ。
つまり、日本の学校や自治体にも、適切な教科書の選定と活用を行うには、実態を踏まえつつ、教科書単体ではなく、教育活動全体の中で考えていくことが求められる。その前提として国は、学校や自治体を支える体制を整備していく必要がある。

津田塾大学学芸学部国際関係学科 教授
1997年に津田塾大学学芸学部英文学科卒業。2003年に広島大学大学院教育学研究科博士後期単位取得退学後、日本学術振興会特別研究員、タンペレ大学大学院客員研究員、熊本大学大学教育機能開発総合研究センター助教授・准教授、国立教育政策研究所高等教育研究部総括研究官、津田塾大学学芸学部国際関係学科准教授などを経て2022年より現職。専門は比較国際教育学。北欧のフィンランドをフィールドとして、主に教育制度や教育政策について研究
(写真:本人提供)
(注記のない写真:JackF/PIXTA)
執筆:津田塾大学学芸学部国際関係学科 教授 渡邊あや
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら