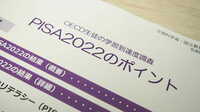北欧で「教科書"紙に回帰"」、「デジタル教科書推進」の日本はどう受け止めれば? フィンランドも異変、学習や健康面から議論
リーヒマキ市の決定は、同市が2023年12月から2024年1月に、前期中等教育段階(中学校相当)の生徒・保護者・教員に対して実施した調査に基づくものであった。調査では、教員から、追加課題の提供など個に応じた教育やデジタル・スキルの開発、評価においてデジタル教科書の利点が認められる一方、スキルの強化、集中力の維持・向上、母語の学習には紙の教科書が適しているという見方が示された。
紙の教科書への回帰を望む教員や保護者の声、デジタル教材の過度な使用による生徒のウェルビーイングや健康への懸念などもあり、一部教科を紙の教科書に改めるという決定に至ったのである。
リーヒマキ市の決定は、あくまでリーヒマキ市のものであり、これを「フィンランドの動向」として語ることは、一般化が過ぎるかもしれない。
しかし、リーヒマキ市に追随するかのような動きもある。2024年10月23日、首都であるヘルシンキ市の議会は、「市内の学校において、デジタル教科書の代替として紙の教科書を提供する可能性を検討する決議」を全会一致で採択した。教育の平等性の観点から、デジタル教科書を使用している場合でも、紙の教科書にアクセスする機会を児童生徒に保障しようとするものだ。
この決議は、高校等、後期中等教育の無償化に関する審議の中で偶発的に行われたものであり、「議題」として予め提示されて議論されたものではない。そもそも、ヘルシンキ市では、使用する教材の選択は学校や教員に委ねられている。そのため、実際の影響は未知数だが、この提案が市議会という公的な場において党派を超えた支持を得たことは、昨今の“教科書の紙回帰”の一端を示すものであるとも言える。
デジタル教材推進の自治体も、背景に「脱集権化」
とはいえ、デジタル教科書をめぐるフィンランドの自治体の対応はさまざまである。リーヒマキ市のようにデジタル教材の推進から紙の教科書への回帰を図る自治体もあれば、デジタル化を進める自治体もある。
例えば、イカーリネン市は、目標とするデジタル教材の比率(40%)を自治体として定め、それに基づいて教科書採択・使用の方針を立てている。タンペレ市では、基礎学校の教科である「環境」や「健康教育」において、地域の実情を踏まえた紙の教材が少ないことやICTリテラシー育成の観点から、近隣自治体と共同でデジタル教材を開発。それをオンライン学習プラットフォームで共有し、活用を試みている。
なぜこのような状況が生まれるのか。その背景には、1990年代以降進められてきた教育政策がある。教育の提供について、国がこと細かに規制することを避け、自治体の裁量に委ねる方針を取ってきた。国が基盤を整備し、実施を自治体や学校が担うという仕組みの構築だ。改革の中で、教科書検定制度も、教科書の使用義務もなくなった。「紙」か「デジタル」かという議論以前に、「教科書」を用いるか否かという選択も含め、自治体や学校は、自由に教材を選ぶことができるようになったのである。
デジタル教科書についても同様だ。国は、その開発や活用について、ビジョンは示しつつも、何をどのように活用するかは、自治体や学校、そして、実際の授業の担い手である教員の裁量に委ねている。こうした教育の「脱集権化」に伴う現場への権限移譲は、地域の実情やニーズを踏まえた対応を可能にする一方で、格差の拡大につながっているとの指摘もある。
実態を踏まえ「教育活動全体」で考える必要性
このような状況を踏まえ、教育のデジタル化に関するさまざまな検証が試みられている。デジタル化が学習環境・学習・前期中等教育段階(中学校相当)の生徒の学習成果に与える影響について調査したDigiVooプロジェクトは、その一例だ。これは、ヘルシンキ大学とタンペレ大学の研究者からなる教育・評価・学習センター(REAL)の研究グループが、教育文化省からの委託を受けて2021年度に実施した調査で、デジタル化と各教科の親和性の検証なども行っている。