環境や特性で「努力できない子」も伸びる、個人の「やる気」に頼らない指導法 宿題ゼロでも「学級平均95点」を実現できる工夫
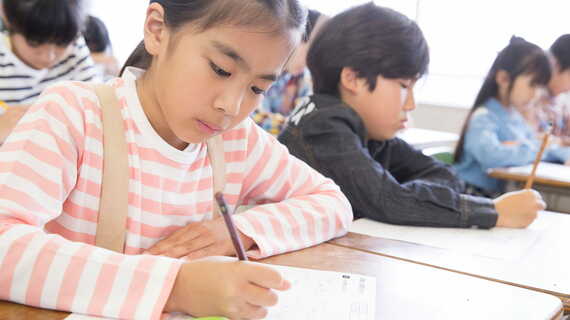
義務教育から「こぼれ落ちてしまう」子たちの存在
――「個人のやる気」に頼る指導法から、現在の指導法に変わった経緯をお聞かせください。
私自身、若手時代は個人のやる気や努力に頼る指導をしていました。例えば「来週、ここからここまでをテストします、合格点は70点」などと提示し、努力できる子は高得点がとれ、そうでない子には「このままだと合格できないよ」など、脅し文句を使うことも。合格点がとれるまで再テストに付き合う。よく言えば面倒見がよいのかもしれませんが、本当に子どもたちのためになっていたかというと疑問が残ります。
――世間一般には、努力できる子とできない子で差がつくのは当然、という考え方もありますね。
そう思う方も多いと思います。でも、私たち教員がその姿勢ではいけないと感じるようになったのは、教員生活も5年を過ぎたころでしょうか。児童たちの家庭をみると、「努力できない環境」に置かれている子の存在が見えてきました。

目黒区立不動小学校 主幹教諭
NPO教育サークル「GROW」6th代表。2020年に同サークルを立ち上げ、「教師として1mm成長する」を理念に活動。東京教師道場リーダー、東京都教育研究員、東京都小学校体育研究会研究部長等を歴任。教職のかたわら、2025年春より大学院経営情報学研究科MBAコースにも在学。小学校体育科副読本「みんなの体育」(Gakken)他執筆多数
(写真:本人提供)
例えば足の踏み場もないくらい、家がものであふれている家庭もあります。学習机を置くどころか、教科書を広げて宿題に取り組むこともできません。努力できる環境が整っていないのに、ただ「努力せよ」と言うのは無茶です。
また、本人や保護者の方が、発達障害など何らかの困難を抱えている場合もあります。勉強や努力の仕方がわからず、その何段階も前でつまずいてしまう子がいる現実も見えてきました。
小学校や中学校は義務教育であるにもかかわらず、環境や特性によってその教育からこぼれ落ちている子がいる――。努力の仕方から教える必要がある子たちに対して、教育のプロとして何をすべきかを考えるようになり、試行錯誤を始めました。
































