
──行政の中でも裏方の仕事、現場で働く人たちにフォーカスしたいと考えた理由は。
研究者になる前は同志社大学の職員として働いていた。仕事をする中で、「大学においてひのき舞台に立つのは教員だが、それをしっかりと支える仕事も大事だ」と裏方の重要さを実感するようになったことがまず1つ。
その後大学院で「実践をつぶさに観察し理論を導き出す研究手法がある」と教わったのだが、とりわけ「早稲田大学の寄本勝美先生はごみ収集車に乗っていた」と聞いたときには、研究というもののイメージが根底から覆された。私がごみ収集車に乗りながら清掃行政の研究をするようになった原点には、そのときの驚きがある。
研究者として大東文化大学に就職した頃、公務員の労働組合である「全日本自治団体労働組合(自治労)」の任期付き研究者のポジションも得た。自治労の紹介で新宿区の清掃事務所を訪れたのが2016年。そこから8年かけて多くの現場に入った経験が本書の基になっている。
収集、中間処理、最終処分という各プロセスで何が起こっているのかを入門書的にまとめた。普段なかなか目にすることのない世界だが、ごみ収集なくして私たちの生活は成り立たない。
──「ごみ収集=行政サービス」のイメージがありますが、民間事業者の取り組みにも多くのページを割いています。

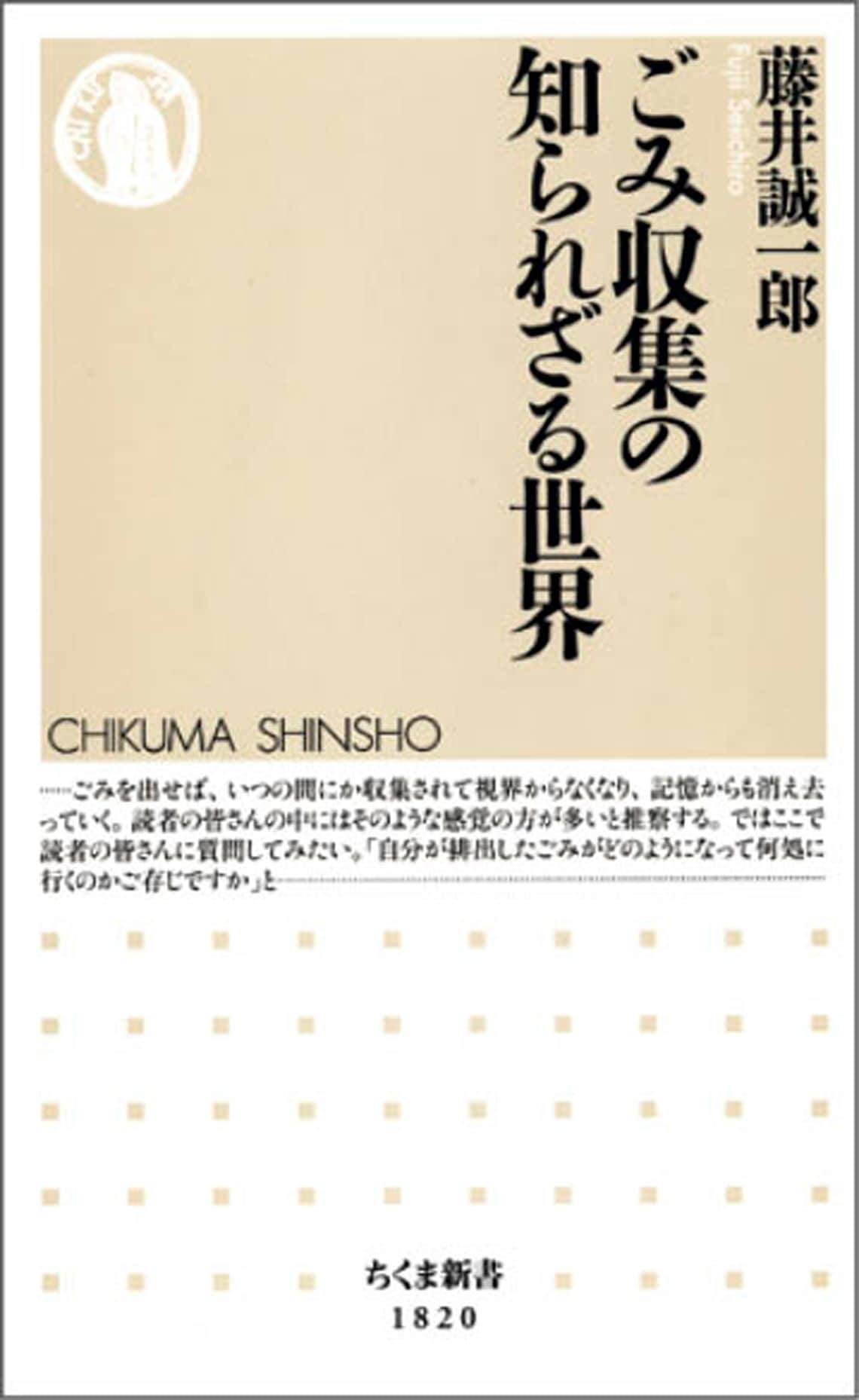































無料会員登録はこちら
ログインはこちら