急勾配区間多い「都電荒川線」意外に大きな高低差 駅ごとにどのくらいの差があるのか調べてみた
次の向原は約30mで、大塚駅前とは12mの高低差がある。王子駅前―飛鳥山間より1m高低差が大きく、この区間の大塚駅前から天祖神社付近までに62.8パーミルの区間最大の勾配がある。「おや、飛鳥山よりも1m高さがあるのに勾配が少し緩やかなのか」と思われるだろう。これは、一気に向原に上るのではなく、階段のように何度か勾配を登るためで、武蔵野台地が階段状の地形なのがわかる。
東池袋四丁目が約28m、都電雑司ヶ谷が約32mで鬼子母神前が約29mとなるが、都電雑司ヶ谷と鬼子母神前間は、停留場間が少し低く、アップダウンの地形となっており、最大勾配は54パーミルとなる。ただし、現在都市計画道路の整備中で、完成すると少し緩やかな勾配になる。
学習院下は約11mで、鬼子母神前との高低差は18mもあるが、停留場間500mを使って42.2パーミルの勾配としている。学習院下から鬼子母神前方向を見ると、長い坂を実感できる。
次の面影橋が約9m、終点の早稲田が約8mと、この付近は神田川の前身となる平川により浸食されたとされる。平川は大きな川でたびたび洪水をもたらしたが、江戸時代に徳川幕府が平川を改修し、現在の神田川に生まれ変わった。
路面電車は人生のようだ
東京さくらトラムは1両編成のかわいい車両だが、急勾配も克服する高い性能を持っている。現在の車両は性能が良くなったが、吊りかけ駆動方式による電車時代は、坂道になるとモーターを唸らせながら、懸命に登っていった。人間が坂道になると息が荒くなるのと同じで、下り坂になると、慎重になる点も似ている。
路面電車は、人が歩く道と同じ標高を走り、登り坂も下り坂も、そして平坦な区間もある。まるで人生のようでもあり、最も親しみのわく乗り物に違いないだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

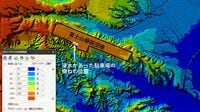





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら