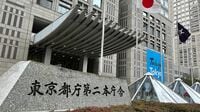都の「スクールカウンセラー雇い止め」に波紋、子どもの継続支援に必要な視点 東京都が前例となる懸念、配置の地域差も課題
しかし、心理職ユニオンが2021年東京都のSCを対象に行った調査では、79%が兼業可能な勤務形態を理想としている。この調査は東京都のSC不再任問題が起こる以前に行われたものだが、常勤を望まないSCがいるのも事実だ。
「SCの中には病院などほかの分野で働く公認心理師や臨床心理士もいますし、『外部性が保たれるほうが専門性を発揮できる』と考える人もいますから、私もすべてのSCが常勤すべきだと考えてはいません。全国には2万7000を超える公立小中学校があり、そのすべてに常勤SCを配置するのは難しく、常勤SCと非常勤SCを組み合わせる体制が現実的だと思います。例えば、非常勤SCでも週2日ほど配置されれば、個別対応や全員面接などさまざまな貢献ができますし、即対応が必要な際は拠点校に配置された常勤SCがカバーするといった体制を取ることができます。実際、名古屋市では全市立中学校の常勤SCが、常勤SCがいない小学校をカバーしています」
SCの雇用形態の整備を求める一方で、SCの質の向上も必要だと石川氏は述べる。
「その子にとってよかれと思ってやったことでも、学校文化やその学校の考え方、方針、地域性を踏まえたうえで活動しないと、独りよがりの活動になってしまう可能性があります。理不尽なことや、独特の文化に戸惑うこともあるでしょう。しかし、そうしたことはどの社会でもあり得ること。そこを理解しながら、『この子はどういう環境や条件が揃ったら状態がよくなるのか』をつねに考え、教員の皆さんと共有することが大切です。また、子どもを取り巻く社会課題にはさまざまなものがあります。私たち協会も職能団体としていろいろな研修を提供していかなければと考えています」
また、学校にはSCをもっと活用してほしいという。
「例えば、各学校では年に3回程度、いじめに関するアンケートを行っていますが、SCがその内容を確認するまで時間がかかる場合が多い。アンケートを実施したらすぐにSCにも共有いただき、気になる回答があれば迅速に対応していただきたいですね。そうでないと子どもは『せっかく書いたのに……』と思ってしまいますし、重大事態になってからでは親御さんと学校の対立という構図の中で子どもの姿が見えにくくなります。そうなる前に、SCがアンケートも含めて日常的な段階から、学校全体で行う人権教育やいじめ防止教育までしっかりと関わらせていただきたい。不登校についても、SCは担任の先生や養護教諭の先生と連携することで、一緒に学級観察を行うなどさまざまなアプローチができます。そうした体制のためにも、SCの配置拡充や継続的な雇用は重要です」
子どもたちへの支援にSCの力が十分に発揮されるにはどうすればよいのか。議論とともにその雇用の安定化が進むことを期待したい。
(文:吉田渓、注記のない写真:metamoworks/PIXTA)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら