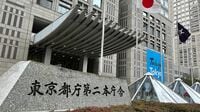都の「スクールカウンセラー雇い止め」に波紋、子どもの継続支援に必要な視点 東京都が前例となる懸念、配置の地域差も課題

こども教育宝仙大学教授、こども教育学部長
公認心理師、臨床心理士、特別支援教育士。国立大学法人奈良女子大学大学院博士後期課程満期退学。公立学校および私立学校スクールカウンセラーとして20年間勤務。2016年こども教育宝仙大学教授に就任、2018年より現職。日本公認心理師協会理事・教育分野委員長。日本臨床心理士会教育領域委員会副委員長。現在、中央教育審議会初等中等教育分科会臨時委員、こども家庭庁いじめ調査アドバイザー、令和3・4・5年度文部科学省いじめ対策・不登校支援等推進事業SC及びSSWの常勤化に向けた調査研究統括
(写真:本人提供)
「私の周りでも、再任用を認められなかったベテランSCの方々がいます。学校の管理職が『なぜこの人が不再任なのですか』と都に問い合わせたケースもあったと聞きます。こうした突然の不再任が起きると、それまで担当していた子どもにも関われなくなり、SC自身の人生設計も崩れてしまいます。会計年度任用職員制度はSCに限らない雇用形態であり、国が決めた制度ですから、SCだけを特別扱いできないのは理解できます。しかし、行政から不再任の可能性を事前に丁寧に説明していただいていれば、衝撃はもう少し抑えられたのではないでしょうか」
石川氏は日本公認心理師協会理事と教育分野委員長を務めており、「ほかの職種の中には『SC事業は縮小される』『SC事業は今後、若手だけで運用される』と曲解される方もおり、職能団体としても、この制度を十分理解したうえでどう対応すべきか、きちんと会員や各所に説明できていたらという反省があります」と話す。
しかし、制度についての理解が進んだとしても、今のままでは子どもたちへの支援の継続性については問題が残る。日本公認心理師協会では、今回の不再任問題を「東京都だけの問題ではない」として、子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、SCを複数年継続して雇用することを国と自治体に求める声明を発表した。
「昨年12月の総務省による『会計年度任用職員制度の適正な運用等について(通知)』には、再度の任用は『各地方公共団体において、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、適切に対応いただきたいこと』とあり、任期の設定は自治体が適切に判断するものと解釈できます。また、『結果として複数回の任用が繰り返された後に、再度の任用を行わないこととする場合には、事前に十分な説明を行う』とも書かれています。今回私たちは、東京都のSC不再任問題が前例となって地方にも同様の事態が広がることを懸念しており、声明を出しました。雇用形態については、子どもたちへの支援の継続性を考慮した見直しが必要ではないでしょうか」
「常勤+非常勤」の体制で支援の充実を
では、SCが子どもたちのために十分に力を発揮するためには、どのような雇用形態が望ましいのだろうか。
「子どもを取り巻く問題はいじめや不登校、貧困の問題と多岐にわたります。しかし、週1日4時間でできることには限りがありますから、目指すのはSCの常勤化です。私は国の委託を受けて昨年度までの3年間、『スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの常勤化に向けた調査研究』を実施しましたが、調査ではSCの54.7%が『常勤を希望する』と答えています。SC常勤化を実現した名古屋市では、全市立中学校で週5日同じ人がSCを勤める形になっています。任期は5年ですが、エントリーすれば更新の可能性があり、一部の人は試験を受けて定年制に移行しています。常勤化によってSCは学校のことをよく理解して日常的に関わることができており、市内のSC同士、心理教育の教材を共有し合うなどのスキルアップも行っています」