今キャリア教育で伝えるべきは「夢は全員が実現できるものではない」こと 職場体験だけに頼らない「第3段階の指導」へ

キャリア教育開始から20年、3つの段階と2つの課題とは
日本で最初の「キャリアデザイン学部」は2003年に法政大学で誕生した。児美川孝一郎氏は立ち上げからこの学部に携わり、20年にわたってキャリア教育の研究をしてきた第一人者だ。同分野の光も影も見てきた同氏によると、キャリア教育の歩みは、次の3つの段階に分けることができると言う。
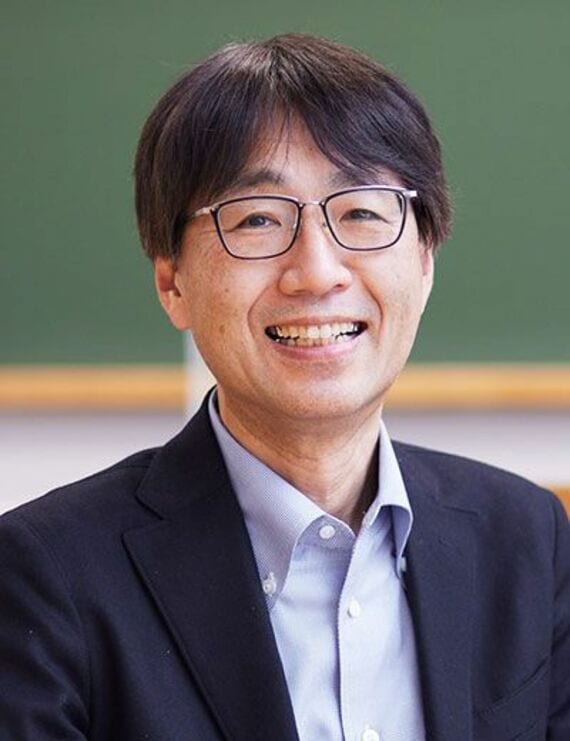
教育学研究者/法政大学キャリアデザイン学部教授
東京大学教育学部卒業、東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。法政大学文学部教育学科専任講師、助教授などを経て2007年から現職。日本教育学会理事、日本教育政策学会理事。著書に『キャリア教育がわかる』(誠信書房)、『キャリア教育のウソ』(ちくまプリマー新書)、『まず教育論から変えよう』(太郎次郎社エデュタス)、『夢があふれる社会に希望はあるか』(ベスト新書)などがある
(写真:児美川氏提供)
「2004年から文部科学省の予算がついて、学校でのキャリア教育が始まりました。背景には氷河期世代やフリーターなどの就職難があり、『勤労観』や『職業観』を説くことで、若い人の就職を目的にした教育が行われた。言い方はよくありませんが、この時期の取り組みはいわば対症療法で、キャリアについての包括的な教育ではありませんでした」
その反省を受けて、キャリア教育は2011年ごろから次の段階に移っていく。
「社会に出ることを『働く』という観点のみで考えるのではなく、市民として、地域住民として生きるための幅広いキャリア発達が考慮されるようになりました。これが第2段階です。近年はさらに第3段階として、学校で学ぶこととキャリアとの関係が意識され始めました。2020年度からの新学習指導要領をきっかけに、教科の勉強と自分の将来がつながっているのだという教育にシフトチェンジしてきています」






























