発達障害の子どもの進路「自己理解」最大のカギ、支援やサポートうまく活用を 特性に適した学校、サポート選びのポイント
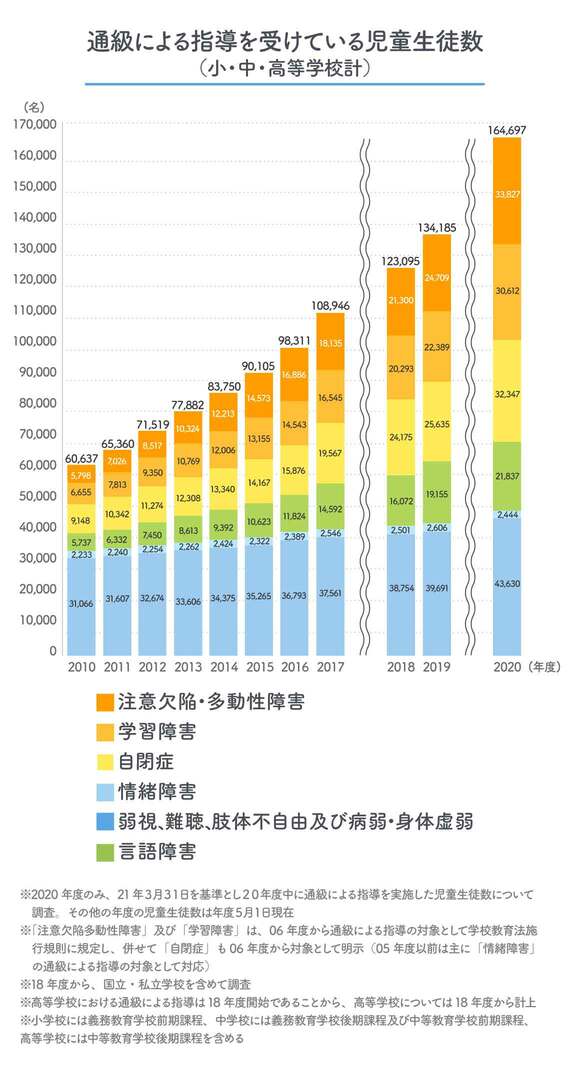
そのほかにも発達障害の子に向けたサポートのある私立学校などがあるが、こうしたいくつかの選択肢の中で、保護者は子どもの就学先をどのようにして決めたらいいのだろうか。長田耕氏は次のように話す。

Kaien 教育事業部 TEENS
(写真:本人提供)
「健診などで発達障害の可能性があると診断されたり、子どもの行動に不安がある場合、自治体に就学支援について相談をすることができます。そこで専門家が面談、検査などを行い、子どもに合った就学先を提案します。ただ必ずしも提案に従わなければいけないわけではなく、最終的にどうするか決めるのは保護者です」
もし特別支援学級に就学する提案を受けても、保護者が大丈夫だと判断すれば、通常学級で様子を見ることができる。ただ通常学級では、十分な支援を受けられないことも多く、学年を重ねる中でこのままでは難しいと判断した場合、途中で所属級を変えることも可能だ。
「グレーゾーンの子どもの場合は小学校3年生くらいで、やはり通常学級では難しいと保護者が判断することがありますね。途中で変更したい場合でも、現状は希望が通らないことは少ないです。ただ学年の途中で変えるのは一般的に難しく、年度替わりで変わることになると思います」(長田氏)
中学卒業後、高校進学時に広がる選択肢
中学校でも、公立は同じように通常学級、特別支援学級、通級指導があり、私立でも特別な支援に力を入れている学校がある。私立に入学するには受験があるため、ある程度の学力が必要となるが、学べる環境を選べるというメリットがある。また不登校の子は、自治体が設置する適応指導教室や民間のフリースクールに特定の学校に所属しながら通うなどの選択肢もある。
「中学校入学時にも、保護者は公立中学校の相談室や教師と、子どもの就学先について相談する機会があります。小学校での過ごし方がポイントになっていますが、保護者の考えと行政(教育委員会)の考えが別の場合もありえます。保護者・本人の希望は受け取りつつも、行政と学校側のリソース含め、対応可能かどうかも加味して案内されています」(長田氏)
高等学校になると全日制の公立、私立に加え、通信制高校、通信制に通う生徒を支援する通信制サポート校、高等専修学校、定時制高校、専門学校などさらに選択肢は広がる。公立に進学する子が多いが、最近では通信制高校、通信制サポート校を選ぶ子も多いという。
「通信制には、発達障害の子どもが学びやすい環境がそろっています。中学校の勉強でつまずいたところはさかのぼって学習ができますし、最近は通信制といっても週に何日か通える学校もあります。1年生は週に1回、2年生は週に3回など、個人のペースや希望に合わせて幅広く選べるのが魅力です。また芸術やスポーツ、ファッション、プログラミングなど、さまざまなジャンルの専門コースがあるのもメリット。自分の興味に合うものを見つけやすく、将来にもつながりやすいと思います」(森谷氏)
早めにサポートを受け、自己理解を深めるのが大切
高校卒業後は、学びを求めて大学や専門学校へ進む、あるいは就職するなど進路は分かれる。その際の選択で大切なのは、本人の希望や適性に合っているかどうかという視点を重視することだ。






























