「給食でアナフィラキシーショック」食物アレルギーの学校対応はどう変わった エピペン注射など教員の意識や除去食に地域差
しかし時代は変わり、現在では文部科学省が学校と、厚生労働省が保育園と、給食における食物アレルギー対応に関するマニュアルや指針を提示したり、消防や医療機関との連携を強化したりと取り組みは進んでいる。一方、栗山氏のヒアリングによれば、食物アレルギーのある子の保護者には現在も次のようなヒヤリハットがあるようだ。
・「こぼれた牛乳を拭いた雑巾を放課後の掃除などに使ってしまい、牛乳アレルギーを起こす」
かつて当事者だった立場として栗山氏は、保護者のこうした不安ももっともだと理解する一方で、「学校現場が尽力していることも冷静に受け止めてほしい」と話す。
「学校の多大な努力について、保護者の理解が十分ではないことは問題かもしれません。学校への期待や依頼が過度になり、現場の負担が増えると、かえって危険や事故につながる可能性もあります。まずは、ガイドラインにある学校生活管理指導表を基に、本人・保護者、学校関係者、医師が話し合うことが大切ではないでしょうか」
「学校でのエピペン使用」は保護者の熱意に省庁が応えて実現
もう1つ、食物アレルギーのある子と保護者、そして学校現場にとって避けて通れない問題がある。それが、アナフィラキシー症状の進行を一時的に緩和するための自己注射薬「エピペン」の使用だ。
現在、学校にエピペンを持参することは認められており、児童生徒がアナフィラキシーショックを起こしてエピペンを自己注射できない状況にある場合には、その場に居合わせた教職員がエピペンを注射することは医師法違反にならないとされている。
しかし栗山氏がアラジーポットを設立した当初は、学校での使用どころか、食物アレルギーの症状緩和の目的でエピペンが一般に使われることはなかった。例外的に国有林で働く林野庁の職員にのみ、ハチ刺されによるアナフィラキシーショックから身を守るための使用が認可されていたという。
この状況を憂慮した栗山氏は、学校でエピペンを使用できるよう保護者の立場から働きかけた。弁護士に法律の解釈を求め、文部科学省・厚生労働省にエピペン使用を打診するなど精力的に活動。紆余曲折を経てようやく、エピペン使用は認められた。
「当初エピペンの使用認可は雲の上の出来事でしたが、関係省庁の担当者の方々が熱心に声を聞いてくださり実現しました。教員の皆さんにもアンケートを取ったところ、『子どもの命を救えるなら』と約7割近くの方が、教職員が注射することに肯定的でした。他人に注射を打つことへの恐怖はよくわかるので、感謝の気持ちでいっぱいでした」
教員が児童生徒のアナフィラキシーショックに直面して気が動転しないよう、学校によっては教職員向けにエピペンの実技研修をするなど試行錯誤が続いている。2012年に児童の死亡事故があった調布市は食物アレルギー専門員として市の教育委員会に管理栄養士を配置するなど、自治体ごとに対応を充実させているケースもあり、「学校現場の対応は年々手厚くなっている」と栗山氏は評価する。
アレルギー対応において学校が注意すべきポイント2つ
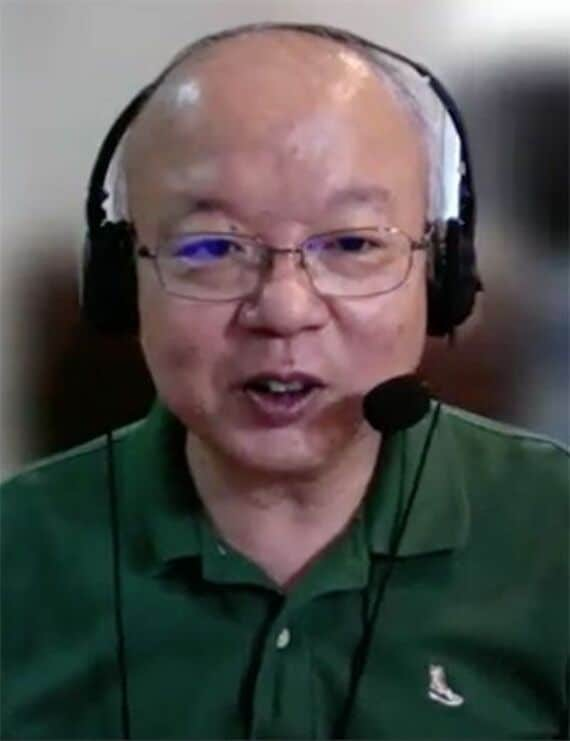
あいち小児保健医療総合センターセンター長、免疫・アレルギーセンター長
名古屋大学大学院医学系研究科 総合小児医療学講座 連携教授、藤田医科大学医学部 アレルギー疾患対策医療学講座 客員教授、日本小児科学会専門医・代議員、日本アレルギー学会指導医・理事、日本小児アレルギー学会理事、日本小児臨床アレルギー学会理事、認定NPO法人アレルギー支援ネットワーク副理事長なども務める
(写真は東洋経済撮影)






























