「不登校」や「うつ」とも関連、発達障害のある女の子の「カモフラージュ」とは? 早期から過剰適応、9歳ごろまでの対応が大事
そうした中、日本では心療内科の現場でもカモフラージュが改めて注目されるようになりました。心身症や摂食障害の受診者の中には、社会適応しようと無理を重ねて症状が出た方が多く、調査すると発達障害の特性が見られるケースも多いことがわかったのです。このように臨床現場から課題が浮かび上がり、児童精神医学の人々も注目し始めたというわけです。
──メンタルヘルスの低下について、具体的に教えてください。
カモフラージュは幼児期の早期から始まりますが、続けていくうちに周囲に合わせたほうがいいのか、自分らしい生き方をしていいのか、その狭間で葛藤が強くなっていきます。また、社交不安が強まるほか、周囲との軋轢によってエネルギーがなくなってしまい、うつや不安障害、場面緘黙(かんもく)といった内在化障害が強くなります。
そして、思春期から青年期には「本当の自分」がわからなくなり、学校ではいわゆる「ぼっち」、孤立の問題も見られます。混乱状態でもがいて心身が疲れてしまうため、メンタルヘルスが非常に低下し、うつや引きこもりのリスクが高まります。さらに成人期以降は「みんなと同じようにしなければ」と無理に結婚したものの、どう子育てをしてよいかわからず虐待してしまうなど悪循環に陥るケースもあります。
海外の研究では、ASD傾向のない女性に比べて高機能(知的発達の遅れを伴わない)ASDの女性の自殺率のほうが高いことがわかっています。そこには「カモフラージュによる同化」と「所属感の挫折」が関連していると指摘されています。
──なぜ思春期以降、こうしたリスクが高まるのでしょうか。
日本では思春期までは義務教育ですので、小さい頃から知っている子と成長していくことが多く、カモフラージュしながらでも何とか適応できます。しかし、高等学校ではゼロからのスタートで、定型発達の子との溝が深まりやすくなる時期。さらに、困り事があって先生に質問しても「高校生なんだから自分で考えなさい」と言われてしまう。それで自分で考えてみたものの、できないと先生に怒られ、自分を責めてしまうのです。そういう状態では勉強にも力が入らず成績も下がりがちに。思春期以降は発達障害のある女の子にとっては「居場所がない」「自分を表現できる場がない」ということになりやすい時期なので、うつなどのリスクが高まるのです。
学齢期から「本当の自分」に戻してあげるフォローが必要
──そうした問題を抱える子には、どのような支援が必要でしょうか。
学齢期から自助グループなどを通じ、「本当の自分」に戻してあげるフォローが必要だと考えています。例えば、私が関わっている自助グループでは、その中で「こんなときは周りに合わせてもいいけど、オンとオフを使い分けよう」「趣味に没頭して自分らしさを取り戻す時間を持とう」と伝えています。
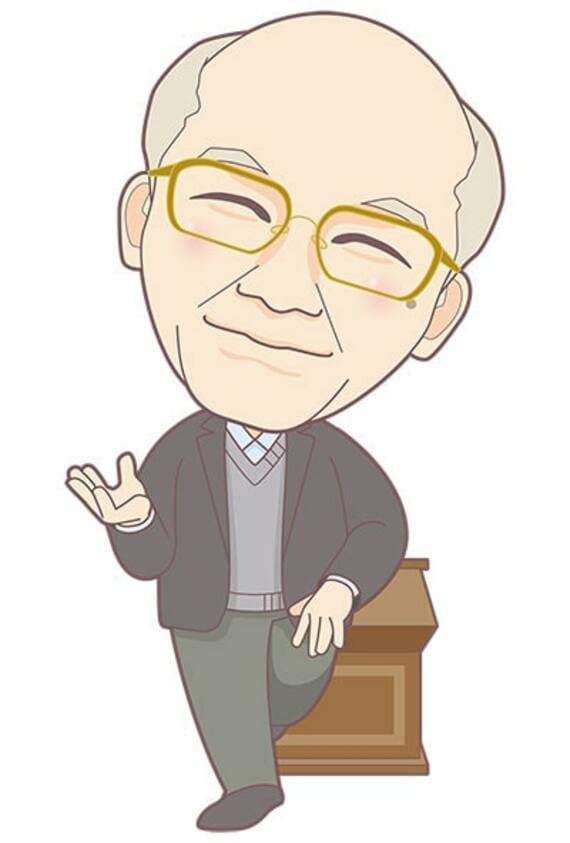
山口大学教育学部附属教育実践総合センター教授、臨床心理士、公認心理師
九州大学大学院教育学研究科博士課程単位満了退学。九州女子短期大学養護教育科講師、同短期大学助教授、1998年山口大学教育学部助教授、2011年より現職。15年より同大学学生特別支援室顧問、21年度より同センター長。専攻は、臨床心理学、ASDへの地域支援、臨床描画法。『子どもの発達支援と心理アセスメント-自閉症スペクトラムの「心の世界」を理解する』『発達障害の「本当の理解」とは』『発達障害のある女の子・女性の支援-「自分らしく生きる」ための「からだ・こころ・関係性」のサポート』『続・発達障害のある女の子・女性の支援-自分らしさとカモフラージュの狭間を生きる』(いずれも金子書房)など、単著や共著多数
(写真:木谷氏提供)






























