護持困難な寺が増えているが、「開かれた寺」には人が集まっている。

丸3年に及んだコロナ禍は、日本仏教の慣習を根底から揺さぶるものとなった。葬儀の簡素化は一層進み、寺を取り巻く経済環境は厳しい状況が続く。一方で、仏教に救いを求める人々は少なくない。コロナ禍を通じて、寺院本来の役割が浮き彫りになっている。
寺の経営を支えているのは主に3つの柱だ。葬儀や法事などの弔いに対する布施、花祭りや施餓鬼などの年中行事での収入、そして墓地の管理費、である。京都や鎌倉などで見かける、拝観料が主な収入である寺院はむしろ特殊といえる。
つまり寺は、定期的に檀信徒が寺に集うことで、宗教的にも経済的にも維持されてきた。だがコロナ禍によって、「3密」回避を余儀なくされた。地域の紐帯(ちゅうたい)としての寺院の機能は途端に失われた。

](https://m.media-amazon.com/images/I/51nM9hHxnoL._SL500_.jpg)
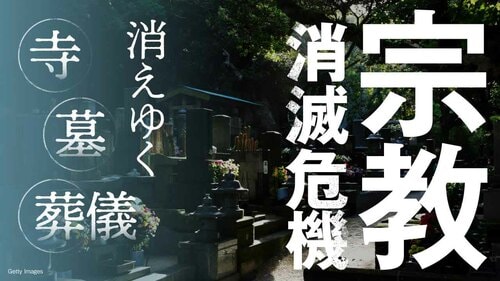
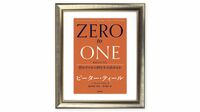
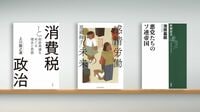
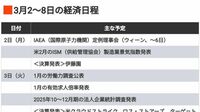






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら