「定期考査と朝課外」を廃止、与論高校が2年間で約30もの「見直し」ができた訳 「主体的な学び」実現のため「観点別評価」へ移行
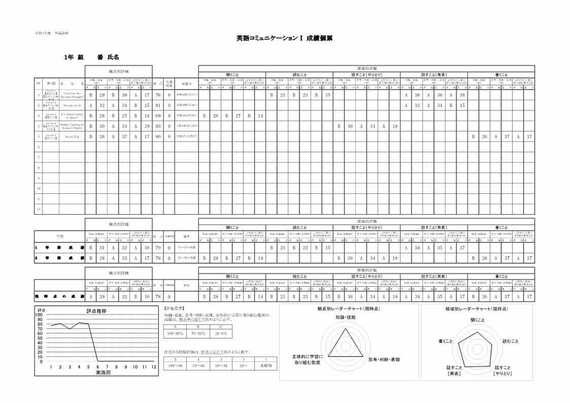
また、テストの日に欠席した場合は別の日にテストを受け、一定の水準に達していない場合は追指導というルールにした。
「当初は全員が同じ日にテストをしなければほかのクラスに情報がもれてしまって不公平だという声も上がりましたが、この運営で何も問題はありませんでした。単元テストは自分の理解度を測るためのものだと説明すれば、生徒は理解するのです」
「適切な指導」と「見通し」で、高校生は確実に学びに向かう
「定期考査や朝課外を廃止したら勉強しなくなるのではないか」という声は学校関係者評価委員などから上がったが、その不安は杞憂だったという。
「競争意識がなくなるのではないかという声もありましたが、本来テストは競争のためではなく、学習内容の定着確認のために行うもの。それを単元別に行うので、むしろPDCAサイクルを回すことが素早く丁寧にできるようになることを生徒や保護者、地域に向けて説明し、理解を得るようにしました。実際、単元ごとの目標などを予告したうえで授業を進めるので生徒はしっかり準備をしてきます」
結果として、学校評価では生徒から「予習がしやすくなった」「慣れたら学力は定着しやすいと思う」といった声が集まり、保護者も「毎日夜半まで勉強している」など、肯定的だ。
「これまでの定期考査は、『テストの1週間前にまとめて勉強するスタイル』を助長していたのだと感じます。自身の成長のために自己管理の力が求められているということは生徒たちにも伝えていますが、適切な指導が行われ、見通しが持てると高校生は確実に学びに向かうことを実感しています」
教員も1年間試行した段階で、「これが本来の授業のあるべき姿だと感じた」など手応えがあったようだ。さらに定期考査の廃止による効果として大きかったのが、探究活動に多く時間を割けるようになったことだという。
「定期考査を実施していた頃は、テスト前を含めて約2週間、行事などを入れないようにする期間が年5回ありました。この制約がなくなり外部と連携する教育活動を入れやすくなったのは大きいですね。本校は現在、東京大学大気海洋研究所の協力を得て、自然科学分野についての課題研究にも取り組んでいます」

また、朝課外を廃止したことで教員に時間の余裕ができ、授業でのICT活用も進んだ。生徒のレポートをオンライン提出にした結果、印刷・配布・回収の負担もなくなったなどの好循環も生まれている。
研究紀要の廃止や生徒指導など「約30もの見直し」を実施
実は甲斐氏は、定期考査と朝課外の廃止だけでなく、この2年間で学校のビジョンに基づき約30もの見直しを実施してきた。例えば、研究紀要の廃止だ。
「研究紀要を作るための研究では意味がありません。それよりも、単元シラバスの充実こそ研究に匹敵すると考えたわけです。実際、本校の教員の取り組みはかなり進化しており、さまざまな研究大会で発表できるレベルになってきています」
学習指導に関するところでは、学年内で共通理解が図れるよう、進路指導室や教科ごとに分かれていた教員の座席配置を学年単位に変更するなどの工夫も。学年内の情報や課題の共有が日常的に行われ、指導の目線合わせが容易になったという。

そのほか授業前後のチャイムや当番日誌の廃止、女子の制服へのスラックス導入、単車通学や携帯電話の持ち込みを許可するなど、これまで課題のあった生徒指導も変えた。






























