オール岐阜で真のDX化、「デジタル・シティズンシップ教育」がカギとなる訳 「こどもファーストのまち」の一大プロジェクト
ワークシートを使ったGIGAびらきの狙いはほかにもある。DX化の基礎となるデジタル・シティズンシップは、子どもだけでなく大人にも必要なものだ。栗本氏は「自治体が大人へのデジタル・シティズンシップ教育をするのはなかなか難しい。まずは子どもを通して、市の大人にも理解を深めてもらうことも目的の1つです」と説明する。
教育公表会で見せた、子どもたちの自律的なICT活用
市教委ではさらに、すでにタブレットを使用している子どもたちに対しても、ルールブックをデジタル・シティズンシップ版に全面改訂して示した。
「従来のルールブックは、してはいけないことを記したいわば『ブラックリスト』のようなものでした。でも新しいものは、できることを明示した『ホワイトリスト』にしました。対象は小学校高学年以上で、最終的には子どもたち自身がルールを作ってくれることが理想です」
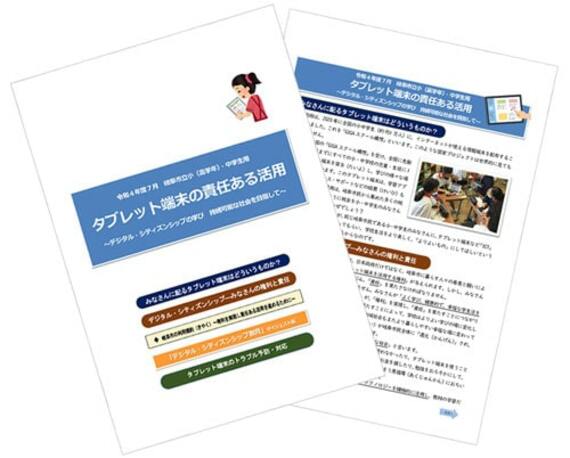
(写真:栗本氏提供)
自らよりよい使い方を考えることこそ、デジタル・シティズンシップの基本姿勢だ。だがインターネットや端末の使用についてのワークショップをすると、「意外にも、子ども同士のほうが厳しく、シビアなルールを作ろうとするのです」と栗本氏は言う。ブラックリストを示すことが主だった旧来の教育からの脱却は、一朝一夕に進むものではないようだ。この傾向は教員側にも見られる。
「実証や新たな取り組みについて、ただでさえ忙しい先生たちに、さらに市からのお願いをしている形です。多くの学校や教員の方に好意的な反応をもらっていますが、その意義や効果に懐疑的な先生もいるかもしれません」
そうした状況を少しでも打破すべく、今年1月の教育公表会で、栗本氏はある作戦に打って出た。発表を行う4つの部会のうち、自身が担当する「教育DX部会」を子どもたちに担当させたのだ。司会進行もパネリストも、2時間の持ち時間をすべて市内の小中学生に任せたという。
「市長や教育長が子どもファーストを掲げていることも、今年の選択を後押ししたと感じています。昨年は『デジタル・シティズンシップ教育推進に係る連携協定』でお世話になっている岐阜聖徳学園大学の教授や、現場の教員に講演してもらいました。そこでDXの姿勢や方針は伝えていたので、今年は子どもたちの実際の姿を見せるのがいちばんだと思ったのです」
準備期間はコロナ禍の冬休み。子どもたちはオンラインで打ち合わせをし、ICTツールを使いこなして原稿をまとめ、プレゼンテーションを行った。探究学習としての深度も感じられる発表に「大人たちもびっくりしました。『あの学校ではこんなふうに使っているんだ』『ここまで子ども自身でできるんだ』ということは、多くの教員にとっても刺激になったと思います」と振り返る栗本氏。「作戦は大成功でした」とにっこりする。
「オール岐阜」で大きなうねりを生み、大人をも変える
不登校児童生徒の支援の1つとして「メタバース」を活用した支援にも挑戦している。注目を集めている仮想空間だが、岐阜市では日時を決めて参加者を募る形で、一度に十数人がバーチャルの世界で交流している。
「不登校の子どもたちもメタバースで同世代の子どもと接し、ゲームをしたりクイズをしたりしています。その中で他者や社会とつながるきっかけになることを期待しています」






























