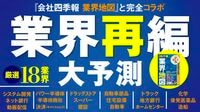ここから3年が勝負、1人1台端末「日常化」のコツ カギは学校のコミュニケーションのデジタル化
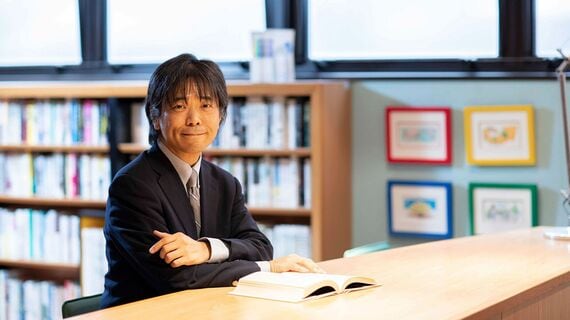
「学校に新しいテクノロジーを導入すると『ワクワク期、やらかし期、安定期』の3つのフェーズで変化が起こります」。こう話すのは、教育の情報化を専門分野とする国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授の豊福晋平氏だ。
「ところが、いろいろな学校関係者から、GIGAスクールの端末が配備されても『やらかし期』が来ないという話を聞きます。子どもたちが日常的に使える状況にしないと『やらかし期』にはなりません。先生方が、保管庫から端末を取り出すきっかけをつかみ切れていないのではないでしょうか」
教育効果を実感するのに必要な前提条件とは
これまでコンピューター室で授業を行っていた頃のように、せいぜい学期に1回、年間3回程度コンピューターを使えば十分というレベルで捉えている学校関係者が多い、と豊福氏は指摘する。
GIGAスクール構想で配備された端末は1台当たり4.5万円と廉価なため、性能的に問題なく使えるのはおおよそ3年と考えると、学期につき1回使用で3年間で9回。授業1回分が5000円だから、結構高い授業料になってしまう。ところが、これを毎日使ったらどうなるか。学校の稼働日は年間平均200日、3年間で600日だから、1回当たり75円になる計算だ。
「GIGAスクール構想はもともと経済対策の一環で、しかもコロナ禍対策として計画が大幅に前倒しされた経緯は覚えておく必要があります。端末を入れ替える3年後、あるいはそれ以降になっても、国から同規模の予算がつくとは限りません。新しい端末に切り替えるための予算の出どころは、おそらく自治体か保護者になります。もし、保護者に費用の負担を求めるとしても、ほとんど保管庫で眠っていたような機器に、4.5万円を払ってくれとは言えないでしょう」
PISA(国際学習到達度調査)2018で、日本は学校教育におけるICT利活用スコアが圧倒的な最下位だった。今やデジタル化が進む社会において、学校だけが取り残されてしまっている中「ギャップに対する危機感がなく、この状況が当たり前になってしまっている」と豊福氏は警鐘を鳴らす。ここで教育のICT利活用を世界レベルに引き上げなければ、もはや教育大国とは名乗れないレベルに衰退するだろう。今取り組まなければ、3年後にはもうチャンスはないということだ。
とくに、これまでは授業にピンポイントでICTを使わせることが多かったが、これからは学内外で端末を使用する「日常化」がポイントになるという。そのためにも豊福氏は「ICTをコミュニケーション手段の中心にすることが必要」と説く。
「ICT活用の教育効果を議論する場合、利用頻度・時間・用途の十分な確保と、それに伴う習熟による総情報量の増加が前提条件になります。先生も児童生徒も、扱う情報の総量を増やしICTに慣れるためには、まずはデジタル連絡帳の運用をお勧めしています。学校で扱う情報は、教科書や教材といったコンテンツより、学校生活全般のやり取りで生じるコミュニケーション要素のほうが多いので、これまで紙媒体で手渡ししたり、手書きで書き取らせているようなことをデジタルに置き換えたりすることで、情報の効率は格段に上がり、便利だなと実感できる境地に達するはずです」
日常化への急坂を上り切り、踊り場に出ると、それまでとは見える景色が違ってきて、ICTを活用した学びに対する目線もリセットされる。そうなったときに、これまでの教員主導型の一斉授業形式から、個別学習やグループワークなど学習者中心のICT活用へと楽に移り変われるという。