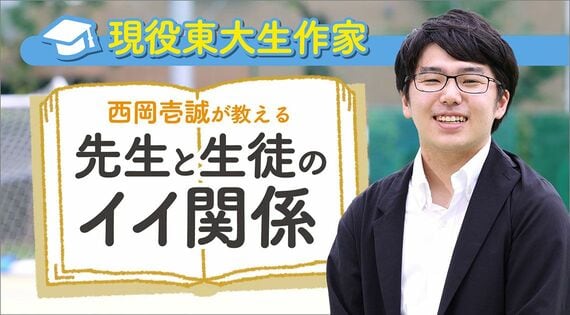生徒が自分なりの問いをいくつも立てられるようになった
武蔵野大中高の場合、探究活動が成績の向上につながることを実証するというのが、この講座を始めた大きな目的の一つであった。
その点では導入からそれほどの時間が経っておらず、はっきりした結果は出ていない。しかし髙橋氏は確かな手応えを感じている様子でこう言った。
「前期の講座を受けて後期の探究活動に入ってからは、生徒が自分の興味ある分野や学びたい学問分野などを明確に掲げ、自分なりの問いをいくつも挙げられるようになりました。実際に見ていて、こんなに問いが挙げられるのかと感じるほどです。ハイグレードコースの偏差値は、これから徐々に上がっていくのではないでしょうか。私は前期の講座をすべて見学させていただきましたが、カルペ・ディエムさんの東大生たちは私たちと扱うテーマも教え方も展開の仕方も違い勉強になりました。私たちの授業に取り入れたいと思う部分もあります」
ここ数年、武蔵野大中高では「チャレンジ」を合言葉に、Project Based Learning(課題解決型学習)を取り入れるなど積極的な改革を推進してきた。その結果、「22年の総合型選抜の大学入試の結果は、非常によかった」と中村氏は手応えを語る。
アカデミックマインド育成講座も、そうした改革の一環として導入したものだが、総合型選抜に限らず一般入試を受ける子たちにとっても意味のあるものだという。学びの型を学ぶことができるからだ。
「探究の力を使って、伸びた子がたくさんいます。勉強する子も増えた。偏差値を上げるためには生徒に刺激を与え続けることが必要です。アカデミックマインド育成講座もそういう刺激になっていると思います。本校がこういう取り組みをしていることの認知や成果が広がって、多くの受験生や保護者にこのマインドの重要性が高まっていくことを楽しみにしています」
成績を上げることだけが目的ではないが、大学入試も知識から思考力を求める入試に変わってきている。高校教育もその対策が求められるのは必然で、同校も含めて今後の推移を注視していきたい。
(注記のない写真:武蔵野大中高提供)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら