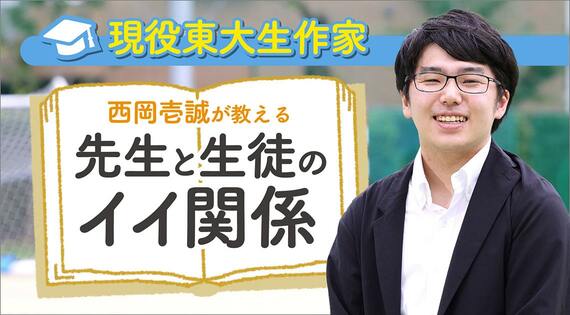今春、2019年に「リアルドラゴン桜プロジェクト」の授業を受けた生徒たちが大学受験に臨んだ。その成果はどうだったのか。
「私たちは、東大に行きなさいという指導はしていません。自分が行きたい大学に行くことが大事だと考えています。ですから『リアルドラゴン桜プロジェクト』で進路をしっかり定め、自分の行きたい大学に挑戦することを期待していました。一橋大学や早稲田大学には合格しましたが、まだチャレンジが足りなかったと感じています。トップ大学を目指せではなく、行きたい大学に行った結果、合格率が高まったのですが、今後の挑戦はもちろん大学入学後やその先の進路について充実することを期待しています」
「リアルドラゴン桜」の授業を受けたい、学外へのPR効果も
一方で、手応えを感じていることとしていくつかの事例を挙げた。
「生徒の学習のモチベーションは上がっています。何事も自分で目標を設定し、計画を立てて取り組むようになりました。授業の復習をする生徒も増えましたし、定期試験の回答用紙が返されると、その結果を振り返るようになりました。先生のところに質問に来る生徒も多くいます。自分がどこを間違ったのかを知ることは、次の実力向上につながります。これが間違いなく『リアルドラゴン桜』の成果でしょう」
そう語る萩原氏によれば、以前は何かいうとすぐ言い訳をする生徒も多かったが、最近は素直に「ありがとう」「ごめんなさい」と言える生徒が多くなったという。また教員も素直にわからないことなどがあれば同僚や先輩に聞く姿勢が身に付いてきたという。「リアルドラゴン桜プロジェクト」の授業を参観し、自らの授業にコーチングの手法を取り入れる教員も出てきたそうだ。
最近は「『リアルドラゴン桜プロジェクト』の授業を受けたいので、頑張って特待生を目指す」と言って同校を受験する中学生も出てきているという。学外にもそれなりのPR効果が広がっているのかもしれない。
「高校教育の3年間は、大学に行かせるためだけの3年間ではありません。卒業後も60年、70年と生きていく、そのときの土台となる部分をつくるための大切な3年間だと私たちは考えています。ですから本校は勉強だけでなく部活動やさまざまな行事にも力を入れています。教育の成果は一朝一夕に出るものではありません。卒業した生徒たちがその後の人生で社会から愛され幸せになれるかどうか、私たちはそこまで考えて教育に取り組んでいるのです」
リアル『ドラゴン桜』で見事に花を咲かせることができるかどうか、もう少し先まで見続ける必要がありそうだ。
(文:崎谷武彦、編集部 細川めぐみ、撮影:今井康一)
東洋経済education×ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら