教育基本法とは?教育に関する法律についてわかりやすく解説
義務教育の目的や、それに対する国と地方公共団体の役割などを規定しています。
1947(昭和22)年に制定された旧法では義務教育期間が9年とされていましたが、現在の法では期間に関する言及をなくし、柔軟に対応できるようにしています。
教育基本法 第2章 第6条(学校教育)
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
学校教育では、規律を守り児童や生徒などが学習意欲を高めることが重要であると規定しています。
教育基本法 第2章 第7条(大学)
2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
大学の基本的な役割について規定しています。
教育基本法 第2章 第8条(私立学校)
国と地方公共団体による私立学校の振興などについて規定しています。
*私立学校の助成に関しては、これまで「私立学校法」と「私立学校振興助成法」が法的な根拠を提供していましたが、本条の文言は私学の立場をさらに強めています。私立学校の「重要な役割」を前提として認めたうえで、「その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない」として、国と自治体側の責務を定めています。
教育基本法 第2章 第9条(教員)
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
教員の研究と修養(※)や、養成と研修の充実などについて規定しています。
※修養:人格を鍛錬すること
教育基本法 第2章 第10条(家庭教育)
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
家庭教育の基本的な役割や公的な支援のあり方などを定めています。
*保護者の教育権が国に優先することを、国内法として初めて明示した条文です。
保護者の教育権に関しては、民法第820条にすでに定められています、本条の「保護者は、子の教育について第一義的責任を有する」によってその優先的地位が確認されています。
教育基本法 第2章 第11条~第15条
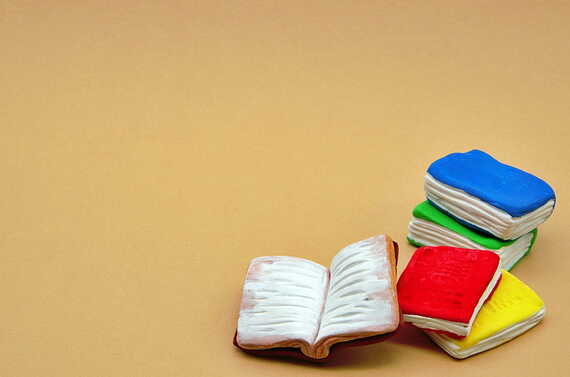
教育基本法 第2章 第11条(幼児期の教育)
幼児教育の重要性と、国や地方公共団体による振興について規定しています。
*本条は、保育所や幼稚園、公園や公民館などの公的施設、民間活動などに、積極的な支援が行われることを言っています。
教育基本法 第2章 第12条(社会教育)
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。






























