関西屈指の進学校・大阪星光学院、企業の経営課題に挑む「探究学習」の中身 教科学習で出合わない難しい課題の解決に奮闘
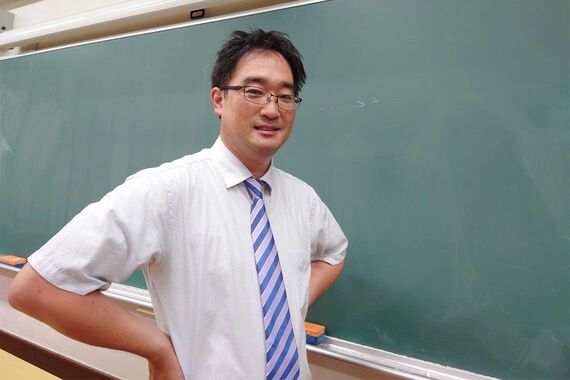
大阪星光学院中学校・高等学校 数学科教諭
「以前から星光学院では、社会との接続を意識させることを目的に、卒業生を中心に多様な分野で活躍する社会人を招き、講演していただいています。そこで講師の方とお話しする中で、ビジネスや経営、マーケティングについて実践的に学ぶプログラムをつくれないかと思い立ったのが、始まりでした」
加えて、もう1つ問題意識があった。「本校は理系志望者が多く、例年だと4クラスのうち1クラスが文系。必然的に特別授業やイベントも理数系に偏りがちです。文系分野の面白さを知ることができる、また文系の生徒も力を発揮できる機会を増やしたいと思っていました」。
それまで大阪星光学院では、全学的な「探究学習」は行われておらず、今回のプログラムは教員にとっても挑戦的な試みだった。
「当初はパワーポイントの使い方やリサーチの仕方といった初歩的なレクチャーも必要かもしれないと思っていましたが、取り越し苦労でした。生徒たちは、教えたわけでもないのに自分たちで調べてパワーポイントの使い方を難なくマスターし、私も驚くような提案書やプレゼンテーション資料をまとめあげてきました」
まさに「探究学習」が目指す「主体的・対話的で深い学び」が実現したわけだが、こうした学びがスムーズに進んだのには理由がある。関西では屈指の進学校として知られる同校だが、知識習得だけでなく、多様な学びを充実させていることでも定評があるのだ。
代表的なのが、中高6年間で約100日間にも及ぶという合宿だ。長野県と和歌山県に宿泊可能な学舎を保有し、生物調査や農園見学などの体験学習、勉強合宿などを実施している。コロナ禍で影響は出ているものの、感染状況を見ながら可能な限り今も実施している。
「寝食を共にし、協力して活動や勉強に取り組む中で、一致団結して目的に向かって進んだり、主体的に行動する力が養われます。グループで何かに取り組むときに生徒たちが発揮する力は、こうした経験から育まれています」と小島氏は明かす。
企業を相手にプレゼンテーション
「星ゼミ探究+」の真骨頂は、生徒が教科学習では出合わない難しい課題に直面し、持てる力を総動員して自分たちでそれを解決しようと奮闘するところにある。

5月に行われた中間発表。各グループが練り上げたプランは、教員やウェルタスから厳しい評価が下された。
「どのグループのアイデアも似通っていて、面白味がない。クライアントであるウェルタスの方からも『もっと斬新なアイデアが欲しい』と指摘を受けました。生徒たちは論理的に考える力は高い。けれど、そうしたセオリーを一度離れて、思い切ったアイデアを出したうえで、それを論理的な戦略に結び付けていくという非常に難しい課題に挑戦させました」































