難解な決算書はビジュアル化し、企業同士や経年で比べることでわかる。さまざまな企業の決算書を図解で攻略していく。

利用客がコロナ禍前の水準に戻るのは難しい(撮影:梅谷秀司)
巨大な装置産業である鉄道業。土地を確保して線路を通し、列車を走らせるビジネスモデルのため、鉄道会社の資産の大半は有形固定資産だ。この固定資産をどれだけ有効に使うかが鉄道会社のポイントになる。列車に多くの乗客を乗せて効率的に輸送することが利益拡大につながる。
しかし、コロナ禍で状況が一変。外出自粛等で乗客が激減し、ラッシュ時に備えて保有する車両は、重い固定費となった。JR東日本の2021年3月期決算は、売上高が4割減り、営業損失は5203億円に。ほかの大手鉄道会社も同様に、大幅赤字に陥った。
トピックボードAD
有料会員限定記事


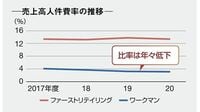





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら