資本主義経済の持つ闇、それを解決できない経済学と格闘した日本人がいる。
今日では世界の人々が環境問題、格差の拡大など資本主義のダークサイドを実感するようになった。だが、半世紀も前からこの問題に悩み、格闘していた哲人経済学者が日本にいた。宇沢弘文(1928~2014年)である。従来の経済学を超克する考え方として打ち出したのが、「社会的共通資本」の思想だ。


宇沢によれば、豊かな社会とは「すべての人々の人間的尊厳と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が最大限に確保できる社会」である。これを、「本来的な意味でのリベラリズムの理想が実現した社会」(『社会的共通資本』、岩波新書)としている。近年は「リベラル」という言葉の使い方に混乱が見られるが、宇沢の定義からは左派でも右派でもない「リベラル」のイメージが浮かび上がる。
そのリベラルな社会の実現の土台となるのが「社会的共通資本」だ。社会的共通資本は、人々が生きていくのに必要なもので、大気、森林、河川、水、土壌などの「自然環境」、道路、交通機関、上下水道、電力・ガスなどの「社会的インフラストラクチャー」、教育、医療、司法、金融制度などの「制度資本」である。

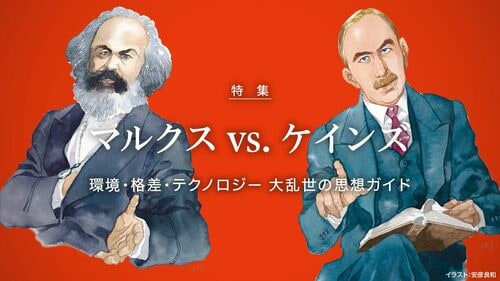
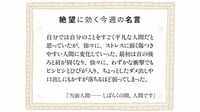






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら