
凶悪犯に死刑、の大前提 精神鑑定はほぼ添え物状態
──既視感を抱かれた光景とは?
植松聖への判決が迫る中、改めて資料を読み込んで気づいたのが、彼の精神状態を正面から問題視する議論がほぼ皆無なことでした。卑劣、邪悪、冷酷などステレオタイプな語彙で悪のアイコンが造形され、罰せられて当然という空気が固まった中で裁判は進行した。
17年前、オウム・麻原彰晃の判決公判で目にした光景がよみがえりました。刑務官に支えられ座っていた麻原は、どう見てもまともじゃなかった。そもそも裁判の途中から彼は弁護団と意思疎通できなくなっていた。ほぼ意識喪失状態の被告を「訴訟能力なし」とはせず裁判は粛々と進行し、一審で死刑が確定。そのとき抱いた違和感、同時期に取材を始めていた死刑問題に対する違和感、植松の裁判はその延長線上にあるとふと思った。急きょ拘置所へ彼に会いに行き、モヤモヤは確信になりました。
──植松の弁護団は、心神喪失状態での犯行であり責任能力なしと主張、それを被告自ら強く否定する経緯がありましたが。



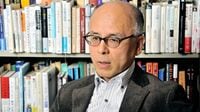





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら