
──事前の指針決定が大事ですね。
例えば、全員の医療ニーズを満たせないときは優先順位をつけざるをえず、場当たり的にルールを決めると、ルールの根拠を説明する時間が限られ、聞くほうも理解する余裕を失っている。また、原則に従っていないと、時間の経過とともに非整合的になる。だから倫理指針は前もって冷静に議論して、決めておく必要があるのです。
──大枠は救命数最大化原則。
倫理学では行為の正・不正をどう規定するかをめぐり、終わりよければよしとする帰結主義、行為に至る意志や義務感を重視するカント主義、人間としてすばらしい行為が正しい行為とする徳理論などが争っていますが、「反証が提示されない限り、より多くの人の命を救うことは正しい行為である」という命題は受け入れられています。
ただ、自明ではない。80歳と20歳の患者のうち1人しか救えないとき、救命数最大化だとどっちを救っても1人だからコインを投げて決めろとなるけれど、若い人を救うべきと考える人も多いでしょう。これは生存年数最大化原則といわれ、一歩踏み込んだ強い原則なので、どの資源に対してどういう使い方をするかなど十分に注意する必要があります。




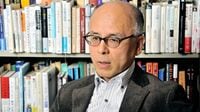




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら